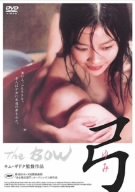BS2 録画

超モダンな家からでっぷり肥えた小おやじが出てくる。
その佇まいや動きが外国の漫画のキャラクタとしてそのまま出てきそうで笑える。
この新築で自慢のモダン邸宅に住むのはプラスチック会社社長のアルペル一家。
同じく肥えた妻はそれが最高の生甲斐であるかのように甲斐甲斐しく家族の世話をし、自慢の邸宅の手入れを怠らない。
そして一人息子のジェラールはどこか無機質なこのモダン邸宅が気に入らない。
金持ちの息子でありながらジェラールは下町の悪がきどもとつるんでいたずらばかりする毎日。
洋服着せられた飼い犬もまた、こっそり家を抜け出しては近所の野良犬と一緒に残飯をあさったりして戯れるのだった。
ジェラールには伯父さんのユロ氏がいる。
ジェラールは両親よりもこの無職で気ままなユロが大好きだった。
最初の方誰も喋らないから無声映画風に最後までいくのかと思ったら、台詞がないわけではない。でもほとんど無いに等しいけど。
トーキー時代の無声喜劇映画といった感じ。
まるで四コマ漫画のようなフリとオチが繰り返される。
誇張しすぎない適度な擬音は見ていて楽しいし、流れる音楽は軽快だし、ギャグや構成に何気なく風刺がきいていたり、何より色使いや建造物、物の配置や動きのデフォルメ具合等々全てハイセンス。
あの超モダンな邸宅のセンスは一体どうよ。
悪趣味でありながら魚のオブジェの噴水や目玉のようになる丸窓がかもしだす愛嬌。
全くもって無駄に蛇行する門から玄関までの道。
庭に敷き詰められる小石はブロックごとに白や青やピンクに緑と色分けされて実に鮮やか。
こんな悪趣味かつ素敵なセンスの邸宅がフル活用されてギャグが展開するんだからそりゃ面白いさ。
建物で言えばユロの住むアパートも凄い。
一体何回増築したのかというくらいのつぎはぎ。
屋上のユロの部屋に行くまで建物間や手前と奥をいったりきたり。
のんびりしてるなぁ。つぎはぎだらけのくせに最高にかっこいい。
図式として新し物好きの上流階級と昔ながらの下町庶民階級の二つがあるのだけど、別にどちらがどうとか言ってる訳ではない。
二つの異質なものは同じフィールド上に並べられ、それぞれの生活の中からギャグが紡ぎだされていく。
どちらも楽しいじゃない。
ジャック・タチの視点は大らかっていうかスケールがでかいっていうか。
それにしても隣家のおばさんは凄いな。ファッションもさることながら、なによりよくこんな凄い女優を見つけたなっていう。