at ギンレイホール
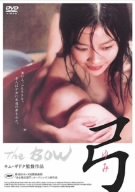
なんですか、この美少女は。
船の上に少女(ハン・ヨルム)とじいさん(チョン・ソンファン)の二人が住んでいる。
じいさんがもう一艘の小型船で釣り客を連れてきて生計を立てる。
じいさんは客を連れてきたり買出ししたりで陸に上がっているようだが、少女はずっと船上にいる。
少女とじいさんに血の繋がりはない。
それどころかじいさんは少女が17才の誕生日を迎えた時に結婚する気でいる。
養父で養祖父で家族で男。
絶対的な信頼関係の二人だったが、少女は釣り客の若い男性に興味を持ち始め・・・
少女の笑みが凄い。
若い男の寝床にまるで子猫のようにするっともぐりこんだ時のあの目。
無垢な少女の愛らしい姿があの目によって一瞬で背筋も凍る妖艶さに変わる。
妖艶さっていうかただもう怖かった。
なんていうか、目が笑ってるんだよ。
「目が笑ってない」という時の目がどんな目なのかいまいち僕は分からないのだけど、「目が笑ってる」っていうのは(もしそんな言い方があるとすれば)この目のことに違いないと思う。
少女はいつも笑みを浮かべている。
じいさんをにらむ仕草ですら、結局は愛情を持った笑みの一種でしかない。
笑みが顔面にこびりつく、って前にもどっかで見たな、と考えていて思い出した。『サマリア』だ。
『サマリア』もキム・ギドクだったよな。
というか今調べたらこの『弓』のハン・ヨルムと『サマリア』のソ・ミンジョンって女優さんは同一人物じゃん。
この子はあと3年の内に健康損なわない程度に映画に出まくってその姿をフィルムに焼き付けておいた方がいい。もったいないから。
舞台は全て船の上で展開する。
小さな船なのになんでこんなに飽きないんだろうね。
年季の入った船体。釣り客用のちぐはぐなソファー。マストも船底も全てが表情を持って活用される。
そして弓。
円く揺れる船に縦横無尽に矢の直線が駆け抜ける。
時が止まったような微笑の前後を、刹那の速さで矢のくさびが打ち込まれる。
時間感覚の崩壊。
緩やかに揺れる時間に打ち込まれる瞬間の死の直線。
弓が何に使われるか。
少女にちょっかいを出すエロおやじどもを威嚇射撃。すげーあぶねえ。
弓占い。船腹に取り付けられたブランコを少女がゆっくりこぎ(水面に足を滑らせながら)、じいさんがブランコのある船腹に描かれた菩薩(?)に向かって3本矢を射る。ブランコには少女が乗っているので矢は少女すれすれを掠めて飛んで船腹に突き刺さる。矢の刺さった箇所で占うっぽい。
弓は楽器にも早代わり。
船と少女とじいさんの佇まいと表情、そしてそこに自由に動きを加える反則的な弓だけで作品になっているという映画。
最後の方、うわー、もっと楽に死ねるのに執念と執着から壮絶な死に方するなぁと思ったら、その後えっ!と肩透かしをくらうのだけど、本当のラストはもっとすごいことになる。
少女の膜を破るのはじいさんか、若い青年か、それとも別の何かか。
「あなたの汚い欲望のために」と非難されるが、じいさんに性の欲望はあったのか。
少女の体を洗うじいさんにいやらしさは無い。
ただ、少女と死ぬまで一緒にいたかっただけなのじゃないか。
若い少女をつなぎ止めるにはもはや結婚するだけでは足りない。
命を代価として魂で契る。
そして一体となった今、少女を囲っていた船は不要となる。
・・・ひとつ気になるのは船が少女を追いかけるように動いて、すぐ力尽きて悲しく沈んでいくように見えたこと。
この船がじいさんの姿そのものに見えてしょうがない。
使えない肉体を捨ててまで少女と契る一瞬間だけに強烈な執念を燃やした結果、そこにいる意味を失った少女は去っていってしまったということ?
まあいいや。
成層圏まで飛んでいたのですかというくらい忘れた頃に矢がズドンと突き刺さって第二の膣が現出する瞬間の官能と戦慄があればいい。
ちなみにじいさんと少女は言葉を発しない。
弓占いの時に少女もじいさんも耳打ちで占い結果を話したりするから喋れないわけではないようだが、一切喋らない。
小さい声しか出せないのか、それとも本当は普通に喋れるのか。(じいさんはともかく少女は普通に喋れそうなんだけど)
喋れないなら喋れない、でいいはずなのに、喋れるかもしれない、と曖昧な設定を加える。
こういう設定の曖昧さを意図してやっているのかは知らない。
じいさんに一体感ともいえる信頼を寄せる少女が、声を出せないじいさんと一緒に暮らしているうちに同じ症状に自然になったのかもしれないし、じいさんが少女を独り占めするために喋ることを禁止したのかもしれない。
とにかく二人が「喋らない」という事実と結果だけがあり、そしてその「喋らない」二人というのが恐ろしく映像にはまっている。
明示されない「喋らない」に至る過程は、映像の細部に不安定な揺らぎを加えて深みを増す。
この監督は瞬間瞬間の撮りたいイメージを撮るのが第一で、ストーリーや設定はイメージを膨らませたりつないだり、見えない奥行きを与えたりするための付属物のよう。
だからストーリーや設定は最低限の説明しかない。
また、あくまでイメージなので、この監督は細部にはこだわらない。
じいさんが弓を楽器として弾くとき、あまりにも音と絃の動きが合ってなさ過ぎて、明らかにじいさんが弾いてないのが分かる。
でもじいさんがこの場面でこういうポーズでこんな音を奏でたんだ!っていうイメージが大事で本当に弾いてる弾いてないなんてことはどうでもいい。っていう考え。
映画によっては気になるのだけど、この人の映画って一瞬と永遠のイメージが相克したスケールのでかい映像を作るから気になんないんだよな。


0 件のコメント:
コメントを投稿