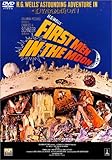※以下、いつも以上に個人的な話愛用の青いママチャリ。7年ぐらい乗っていただろうか。
高校の頃一度トンボ型3段ギアの自転車に乗っていた気がするがそれ以外は一途にママチャリを愛用している。
この自転車、3回盗まれている。
1度目は蒲田で盗まれ、何日かして蒲田の全然違う場所で偶然発見して持ち帰る。
2度目は実家の団地の1階駐輪場に置いていたら盗まれた。
新しい銀色のママチャリを購入して乗り出す。
数ヵ月後警察から電話が入る。自転車が見つかったと言う。
交番に取りに行くと恐ろしい姿に変貌したマイチャリを見る。
前かごは取り外され、ハンドルは鬼ハン仕様、リアキャリアの後部は申し訳なさそうに斜めに折り曲げられ、ださいステッカーまで貼られている。
「あなたの自転車ですか?」と聞かれて思わず吹き出したが「そうです」と言って持ち帰る。
数日後、大学でいそいそ遊んで帰ると、親が今日下に自転車屋が来ていたから直しておいたと言う。
見に行くと、ハンドルは新しく付け替えられ、リアキャリアは見事に矯正され、なにか形的にバランスの悪い前かごまで付けられていた。
ちょっと不恰好なこの自転車より、新品の銀色チャリの方がよかったが、なにか惹かれるものがあったため銀色チャリは姉にゆずる。
数日後、地元の図書館で勉強していると突然中学生程の少年が「まじむかつく!」と叫んだ後、壁やドアをおもいっきし蹴っ飛ばしながらなにやらぼそぼそつぶやいて閲覧室を出て行く。
閲覧室でくっちゃべっていた奴がいたから勉強に集中できなくてぶちきれたのだろう。
直接言えよ直接。とりあえずこんな輩とは関わりあいたくない。
閉館後、自転車置き場に行くとオーマイガー!!マイチャリが苦しそうにぶっ倒れている上に前かごがぐにょぐにょにひん曲がっているじゃないか!
手で曲げられるような硬さじゃないのに、工具でも使ったのか?一部かごが破けている部分まであるし。とかそんなことはどうでもよく犯人は確実にあのアホな少年だろう。
久しぶりに腹が立ってなにか蹴飛ばしたくなったがそれはあの少年と同じなので思いとどまりかごのへこんだりしている部分をなんとか手で直す。それでも変形と破れた痕は生々しく残ったのであった。
2000年12月、蒲田で再び盗難される。
40分以上かけて歩いて自宅に帰る。
4日後、出かけるときにふとエレベーターホールの自転車置き場に置いてあった自転車になんとなく近づいてみる。
ん?色、形といい、かごの破れといい、正しくマイチャリ。
オー!マイチャリ発見!
もしやあの日蒲田まで自転車でいかなかったのかと考えてみるが、バスに乗った記憶もましてや歩いた記憶も全くない。間違いなく自転車で蒲田に行きそこで自転車は失踪した。それに私はいつも自転車は1階に置いているからエレベーターホールにあるわけがない。
・・・自分で帰ってきたのか。
蒲田で消えたチャリが今我が団地の我が住んでいる階のエレベーターホールにいるという事実にぞっとする。
親がどこかで見つけて持ってきたのか?いや、そんな話聞いてないし鍵もかかったままだ。
自転車には住所も名前も書いていない。私の住所と私の自転車を知っている人。自転車見つけてくれたあの警官?にしても黙って置いていくわけないし。
とりあえず戻ってきた事は確かだし、この日は姉に譲った銀色チャリを借りて出かける。
翌日、夜、母と自転車の怪異について話していると「鍵はちゃんと開くのか?」と聞かれる。
未確認だが、見たところ鍵の種類が変わっているとも思えない。
「なんで確かめないんだ!」と怒られる。
私は考えもしなかったが、母は団地のこの階の住人が盗んだ可能性を考えているらしい。
怒られた事にむっとして、確かめりゃいいんだろと怒って鍵持って行ってみる。
まさかと思ったが鍵ははいらなかった。
偶然にも蒲田で私の自転車を盗んだ犯人はこの階の住人だった。
だが、どうすりゃいいんだろう。
さらに翌日、母と一緒にもう一度鍵を確かめに行ってみる。
家を出るとちょうど初老の小柄なばあさんがエレベーターを待っていた。
人がいるところであまり話したくないなと思いつつ、親とやっぱりうちの自転車だよねと話している間中、ばあさんは興味ありげにこっちを見つめ続ける。
ばあさんがこちらに近づいてくる。
「それ、おたくの自転車ですか?」
そうだと言うと「ああ、ありがとうございます」と言うので驚く。
このばあさんは一体何を言っているのか。
話を聞くと、ばあさんも自転車を失くしたらしく、それで雑色駅のすぐ近くにあるスーパーの駐輪場で自分のによく似た私のチャリを発見し、鍵も合ったので持ち帰ったそうだ。
母はしきりにこのハンドルやかごは別物をつけた奴だとかリアキャリアの直しの跡などを説明する。
ばあさんは家から鍵を持ってきて「ほら開くでしょ」と実演して見せ、「あたしも鍵が合わなければ持ってこなかったんですけどねぇ」と言う。
このばあさんも耄碌してただ自分の自転車と間違えたのだからそんなに責めなくてもと思いつつ、ひとまずこの自転車が私のチャリだということに納得してもらったので別れてそれぞれの家に帰る。
母は怒っていた。
あのばあさんはちょっと変人と噂されている人らしく、言ってることもめちゃくちゃで絶対ばあさんが盗んだと言い張る。
よくよく考えてみると最初の嘘とは思えないセリフ「ありがとうございます」で驚くと同時にこのばあさんは悪くないと思い込んでしまった。
だからただ間違えただけなのだと。
しかし自分の自転車だと思っているのならおたくの自転車かなどと聞くか?むしろ私の自転車になんか文句あるのかくらいの勢いで私と母を問い詰めるべきだろう。
それに私と親の会話を耳にしてもしや自分の自転車じゃないのではと思ったのなら二言目に「すいません」と言うべきがいきなり「ありがとうございます」とは何なのか?
ばあさんが最後に言った「じゃああたしの自転車はどこなのかしら、下にあるのかしら」というセリフにも母は大激怒した。
確かに失くしたと言っているのに「下にあるのかしら」じゃないだろ、って。
っていうかなんでこの支離滅裂なばあさんの話に聞いてるとき私は疑問を持たなかったのだろうかという一点にげんなりする。
さらに翌日、大学行くために家を出てふと見ると私の自転車がない。面白すぎて笑ってしまった。
帰りに見たらあったからこの日ばあさんが乗っていたということだ。
この事実を話したら(何度も書くが)母は激怒した。
さらに翌日、以下聞いた話、私は見ていないが母の話ではこの日もやっぱりばあさんが乗っていたらしい。
たまりかねて母は近所のおばさんと共にばあさんの家に問い詰めに行った。
ばあさんは「えっ?あたしが?」とすっとぼけたり、自転車はどこで買ったのかという問いに商店街の店だとかオリンピックだとかとにかく言ってることがめちゃくちゃだったらしい。
暫く問い詰めているとばあさんの夫が出てきて全て判明する。
夫の会社(工場)が蒲田にあり、夫は妻(ばあさん)の鍵を失くしたという話を聞いて、車で蒲田に止めていた私のチャリを工場まで運んで鍵を壊したらしい。
おい、雑色のスーパーで見つけたんじゃねーじゃん。鍵が開くのを実演して見せたのだって自分で付け替えたのなら開くのは当然だし。
さらに翌日、ばあさんが家に来たらしく「蒲田で探したら私の自転車ありました、すいません」としきりに謝って帰ったとのこと。
ばあさんの自転車を教えてもらって見てみたら確かに私のと一緒で青系の自転車だがどっからどうみても全然違うじゃん!
ついでだが・・・
その2日後くらい、母が自転車で事故った。
車の運転手は「かんべんしてくれよ」と言って逃げたらしく、他にも周りにいた人たちの自分に対する冷たさにさんざん文句を言っていた。
ってつまりまあ軽症だったのだけど。
母の怒りは収まらない。警察に乗り込んで行って大分経ってから戻ってきた母は苦笑い。
なんのことはない、その事故った交差点は信号があったそうだ。
長年それに気づかなかった母は猛スピードで信号無視して突っ込んではねられた。
たいした怪我じゃないからよかったが。
2001年の夏には硬かったサドルに柔らかいサドルカバーを装着。
タオル生地の薄いシュラフも購入して自転車旅行へ。
東京から日光、水戸、霞ヶ浦とぐるっと北関東を回ったのも愛用のこの青いママチャリだった。
日光の坂を下った朝6時には前輪ブレーキのワイヤーがぶちきれる。
苦楽を共にした思い出のママチャリ。
話は今日に戻る。
朝からしとしと雨が降り続ける。
傘をさして歩いて蒲田に行く。
会社の駐輪場に置きっぱなしだった自転車を引きずってパンク修理のため自転車屋に持っていく。
修理をお願いして店員の兄さんがチェックすると「ああ、これはもうタイヤもとりかえなきゃ駄目ですね」と言われる。
そういえば3,4年前にも別の自転車屋でそんなこと言われた記憶がある。
タイヤとチューブを取り替えるといくらになるか聞くと、4千円弱だと言う。
一瞬迷ったがお願いする。
1時間後くらいにできると言うので名前と電話番号を書いてマックに向かって歩き出す。
大分歩いてから電話が入る。
店からで、「ペダルの方に違和感を感じませんでしたか?」と聞かれ、なんの話かと思ったらペダルががたがたで中の軸も壊れてしまっていて直すとなるとさらに4千円弱かかると言う。
う~ん。とりあえず修理を待ってもらって店に戻る。
店で店員の説明を聞いてペダルの状態を見せてもらうと確かにがこがこだ。ずっと前からそんな感じだったから気にしていなかった。
考えてこの愛着のあるママチャリを思い切って処分しようと決意する。
タイヤの溝は磨り減って完全に消失し、ベルは自転車買って二月くらいで盗まれたままで、ライトは3年前から点かず(何度警官に呼び止められたことか)、防犯登録の番号の一部は盗まれた際に削られ(何度警官に怪しまれた事か)、サドルカバーには細かい穴が開いてしまったらしく雨の日から3日経ってもサドルに座るとケツがパンツまで濡れるから見た目は悪くともスーパーのビニール袋をサドルにほぼ常にかぶせていたし(サドルカバーを外せばいいという話だが)、さらにはペダルがガタガタときたらこれはもう。
とりあえず持って帰ってゆっくり次の自転車をネットや店で調べようかと思ったが、ちんたらしないでこの店で買ってしまおうかと思う。
店にある自転車を見せてもらう。
かごと荷台が付いてるのがいい。長距離、例えば東京から京都にも耐えうる自転車がいい。MTBもいい。折りたたみもいい。
決められない。というかパンク修理に来ただけなのにいきなり別れが訪れたことへの戸惑いが消えない。
未練がましいことは言うまい。
最後に店員に勧められた自転車を思い切って買う。
が、金がないため一先ず銀行へ行く。
出るときにあの自転車はどうするかと聞かれ、処分をお願いする。
ああ、そういえば今まで自転車の買い替えは全て盗まれた契機だったな。自らの意思で終止符を打ったのはこの青いママチャリが初めてだ。
店の外から既に店内に運ばれている私のチャリを見やると、あの歪んだカゴがにこやかに笑いかけているみたいだった。
金を持って店に戻ると青いチャリはどこかにやられて消えていた。
代わりに購入した自転車が置いてある。
さて、問題はこのニューチャリだが色が微妙だった。
クリーム状のうんこ色に前後輪の泥除けとチェーンのカヴァーが艶のある黒色で、うんこ色も微妙だが黒との組み合わせもまた微妙。
店員はこの色や取り合わせがかっこいいと言う。
のせられて買った自転車だが青いママチャリの後継機、大事に使おう。
と思った矢先から駅近くの違法駐輪の列に止めて雨ざらしで飯田橋へ。このくらい耐えてもらわねば。