at ギンレイホール

もうちょっとスピリチュアルな映画かと思ったけど、なんか普通の映画だった。
ニュージーランドのマオリ族の話。
K-1とかに出ているTOAはこういうところで育ったんだねぇ。

バーナデッドは孤児院に暮らす。
バーナデッドがなにやら孤児院の鉄柵に群がる5,6人の男の子と話をしている。
「キスさせろよ」とか「足を見せてみろよ」などと言われているがまんざらでもない様子。
授業が始まるかなんかで建物に戻るバーナデッドを窓から見下ろす人の影。
次にはバーナデッドの剥ぎ取られたベッドが映し出される。
それで今度はローズ(ドロシー・ダフィ)の話・・・
ってもうなにがなんやら分かんない。
ローズは赤ん坊を生んだばかり。しかしローズの母親は孫である赤ん坊を見向きもしない。
結婚もしていないのに子供を生んだローズを許せないらしい。
ローズの父親も出てくるが父親も同じ考え。赤ん坊を養子に出す手配まで既に済ませている。
「赤ん坊をもらっていくよ」と無慈悲に言う神父。赤ん坊と引き離されるローズ。
この映画の概略を知っていれば特に混乱もしないだろうが、僕は全く知らないで見たので、ここまでで結局なんの映画なのかよく分からなかった。レイプ後の会話もなんも聞かしてくんないしさ。
ただ、もう今年のベストファイブに入れようとは思った。
3本の線はこの後1つの閉じた空間に収まり、この映画の"本題"が始まる。
主役の3人の女性は美人といった感じではない。
マーガレットは寺島進系の顔立ち。バーナデッドは目がでかい。ローズはおっとり系でかわいいのだがかわいくないのか分からない。
この微妙さがリアル。
そしてあまり美人でない3人がなぜか非常に美しい。
目がねぇ、すごいんだよ。
院長の底の見えない深い目、マーガレットの荒みきるぎりぎりのところで止まった目、ローズの常に涙を湛えているような優しい母の目、バーナデッドの折れない信念を持った強く真っ直ぐな目。
バーナデッドの目のドアップ(目のラインに凝固した血)、ラストの方、バーナデッドの静止映像、そしてクリスピーナ(アイリーン・ウォルシュ)の最後のシーン。忘れられない。
で、メニューが結構たくさんあったので、今日も行ってみる。
日替わり定食のマーボー豆腐セットを食う。
これも結構量があった。
味もめちゃくちゃ美味いって程でもないが、まあまあ美味い。
店内の雰囲気は明るい。それというのも奥さんらしき若い女性が気さくに明るい人だから。
作業員らしき客と親しく打ち解けて会話をしている。
客はだれもこれも常連といった雰囲気をかもし出している。
・・・そしてなんだかキャバクラみたいな気がしてしまった。
値段は650円くらいからで、暢と変わらない。
学生はあまり来ないだろうな。
暢と違うのはメニューの豊富さとスタッフの多さかな。
これからどうなるだろうか。
買ってから急いでフィルムセンターに向かう。
なんか外堀通りでデモ行進をしていた。
「いっしょに歩きましょうよぅ~」っておばちゃんが言う。無視した。
みんなプラカード持っていて、戦争反対とかブッシュを火星に、とか書いてあった。
自衛隊のイラク派遣に対するデモ行進。
パンを食いながら眺める。
フィルムセンターに着く。中に入ると、一瞬緊張する。
海淵30分前の16:00ちょうどくらいに来たのにロビーにはほとんど人がいない。
昨日あれだけいた異様な程詰まって入っていた人間がなぜいないのだ。
きょろきょろしていると、本日の当日券は完売しましたの文字が見える。
がくーんと来た。
とりあえず外に出て、食い残したパンを歩きながら食う。結構美味い。
それからまた未練がましくフィルムセンターまで戻ってきて、たばこを吸う。
フィルムセンターの前に灰皿が置いてあったから。
千代田区は本当めんどうだ。
ここにいてもしょうがないので、八重洲ブックセンターに行く。
外堀通りにはまだデモの列が続いていた。
いろいろ立ち読みしてから腹いせに蓮實氏の『監督小津安二郎』と『映像の神話学』を買う。いずれも文庫。
いつ読むんだろうな~。
それからABCマート行ったり阪急行ったりとうろうろしてから19:00過ぎに電車に乗って帰る
当日券を買って、中に入り、席を確保してからロビーで先ほどampmで買ったワッフルを食う。
そんで、よし、2時間ぶりにたばこを吸うぜとうきうきして喫煙所に行くと、喫煙所がない。
健康法がどうのこうので禁煙になりましたから喫煙者の方には大変ご迷惑をおかけしますなんたらと張り紙があった。
もう我慢できないので外に出て、ampmの脇にある路地でこっそり一服する。ふ~~。

物語は小料理屋から始まる。
男が3人。間宮(佐分利信)、平山(北竜二)、田口秀三(中村伸郎)の3人。
そして女性が2人。三輪秋子(原節子)とその娘アヤ子(司葉子)。
秋子の夫の7回忌に集まっているらしい。
女性2人が早々に帰った後、男3人が会話をする。
それがなんか下品なのだ。面白いけど。
男3人は仏さんの三輪の、大學時代の旧友らしい。そして3人とも秋子に思いを寄せていた。
しかし、なんかこのおっさん3人、やらしい。そして失礼。
大學出の裕福なエリートという印象が嫌悪感に拍車をかける。
と言いつつ会話の面白さに結構笑っていたのだが。
観客は若い奴も多かったが、それでも大半は年配の人だった。
僕はつつましく笑っていたが、この年配の人たちはガハガハ爆笑していた。
そして年配の笑い声と共に若い女性の大きな笑い声も聞こえる。
それで思ったのだけど、映画好きの若い女性って総じて変な奴だなって。
もしくは無駄にプライド高そう。
じゃあ映画好きの若い男はどうかって考えると、自分も含めて80%はただのアホだろうと思う。
ああ、この映画のストーリーなんだけど、秋子の娘が年相応の年齢なので、結婚相手を世話しようっておっさん3人が動き出すことで・・・まあいろいろ起こる。
ストーリーはとりあえずいいや。それより僕がこの映画を見たのは岡田茉莉子を見たかったからなんだな。
百合子役の岡田さん、なかなか出てこない。やっと出てきたと思ったらなんかあんまし出番がない。
岡田さんに関してだけ少々消化不良具合を感じて見ていたら、いやいや、さすが、最後のほうに素晴らしい見せ場がある。
百合子があのおっさん3人と対決するのだ。
痛快でキュートでさいこーに素晴らしい岡田茉莉子が見れて大満足。
ちなみにこの場面の時には、おっさん3人に少なからず愛着と愛おしさを感じたりなんかしちゃっていた。
愛すべき登場人物たちの喧嘩後の仲直りにはほっと和む。
和みの見せ方にも百合子とおっさん達の和み方と、秋子アヤ子の和み方の2種類あって、全くタイプが違うのだがどちらも素敵に和む。
原節子と司葉子の会話は相変わらず不思議な空気を醸し出していたな。
相変わらずって表現はおかしいか。
この作品で東宝の司葉子を小津が借りたので、その借りとして東宝で撮ったのが『小早川家の秋』らしい。
そういえば秋子の夫は佐分利信よりいかしてたってことだろう?どんなやつだったのだろう。
壁に貼っついているメニューを見ていたらどれも1200円以上する。
エビフライとかステーキとか20個くらい書いてあり、まあ目が悪くてよく見えなかったのだけど、もちろんライスも付いてその値段だよなぁと探していると、おばちゃんがお冷を持ってくる。
ランチメニューとかないですか?と聞くと、あると言うのでそれを頼む。
周りを見るとみんなランチメニューを食っていた。
オムライスとミニハンバーグ(キャベツの千切り付き)と味噌汁で750円。
これが結構美味い。
オムライスにとろっとかかるソースはなにかと思えばカレーだった。
ランチメニューって日替わりかなぁ。ランチメニューは1つしかないみたいだからある程度の周期でもちろん変えるのだろう。
また行こう。
夜、冷蔵庫のものを全部使ってしまおうと思う。
サイズの小さい人参1本を半月切りにして、卵も1個割りいれて適当に炒める。
チューブ入りのバターも使ったが、よく見たら品質保持期限が昨年の11月だった。おかまいなく使う。まだ半分くらい残っている。
ご飯を炊いていないので主食は餅2個。
できあがった料理を見て、少しも食がそそらない上に、量もこれだけ?と思って、失敗したなと思う。
テレビを付ける。面白いのがないのでBS2でやっているヒッチコックの『鳥』を途中から見る。
なんか集中できなくて、やめようかと思ったが、そういえばラストってどうなんだったっけ?と思って見続ける。
そしたらもう、すぐはまってしまった。面白すぎて。
子供達が鳥の大群に襲われるシーンなんか、カトちゃんケンちゃんゴキゲンテレビみたいな合成なのに、その迫力と子供達が叫びながら走り逃げる姿に涙してしまう。
流れ出したガソリンに火がつき、ガソリンスタンドに向かって火が走りぬける緊迫のシーンがあるのだけど、その時の映し方、登場人物の息を飲む姿の映し方が面白すぎて爆笑できる。
店の中はこじんまりしている。
店のおばちゃんと買いに来たおばちゃんが世間話をしている。
なんかそれほどおいしそうじゃないなぁと思いつつパンを物色していると、壁にサインがかかっているのを見つける。
ぶらり途中下車の旅 阿藤快。
店のガラスにでっかい文字で書いてある天然酵母という文字にひかれて、なんだかなぁといいつつ阿藤さんも入ったのだろう。
かぼちゃあんぱんとマフィンとハムカツパンと揚げパンを買う。
会社に戻ってから、まず揚げパン。
かって~。
まぶしてある粉砂糖もなんだかべっとりしている。
でかいから半分くらいで飽きた。
次にハムカツパン。
衣がバリボリバリボリうるさい。
食うのに飽きて、後は残しておく。
夕方頃腹が減ってきたので、マフィンを食う。
これはかなり美味くてびっくりした。
甘さもちょうどいいしふわふわしているし。
22:00近くまで仕事して帰ろうとすると、今やってるプロジェクトの管理職の人と一緒に帰ることになる。
この人は蒲田の駅まで歩くが僕は自転車をこの会社に止めてある。
ちょうど本社に戻る用事もあったし報告もいくつかあるので一緒に蒲田駅に向かって歩く。
と、どういうわけか軽く焼肉屋で飲むことになる。
管理職の人は「夕方少し食べたからあまり食えない」と言ったが、がしがし焼いて食っていた。
僕は食い足りなかったけど、ビール2杯目を飲み終えたところで店を出る。30分程度しかいなかったか。
2人で5000円くらいで、おごりになるかなぁと思ったが1500円頂戴と言われる。
小銭がなくて2000円を渡そうとすると、「そんなにいらない、1000円でいい」ということになってちょっと得をする。
週間少年マガジンを買って帰る。
マガジンは毎週買って、一通り全部読んでいるのだけど、それほどどうしても読みたいってわけじゃないんだな。
むしろ立ち読みで済ましている週間少年ジャンプの方が生きがいになりつつある。
読むのが遅いので2時間くらい読んでいて、それからこたつを出る気になれずにそのまま寝る。
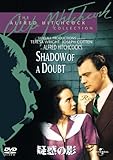
叔父は本当に犯人なのかなぁってわくわくするが、予告編で物語の2/3を見てしまったのではないかとも思って不安になりながら見始める。
いやぁ、取り越し苦労。抜群に面白い。
このしっかり踏みつけて進むテンポ、飽きない安定感、緊張感。
そしてなんともやるせない不思議な感情を呼び起こす。親の、姉妹の、親族の、人間の愛の映画。

『フリーダ』のサルマ・ハエックはやっぱり眉つながってないんだね。
ジェーンフォンダが映画の仕事でしか体験できないこととして、役になりきったとき他の共演者や監督、スタッフの全てと溶け合って一体になっている感覚に陥ると言う。その時はSEX以上の快感だそうだ。
演技の究極の形だな。ジェーンフォンダ、65歳。

と、その前にこの映画の大まかなストーリーを書いておこう。
チャーリー・カウフマンがスーザンというニューヨークタイムス紙の女性記者が書いたノンフィクションの脚色を依頼される。
さっそく取り掛かるものの、全く書けない。
脚本を書けないこの内省的で恋人とも今一歩踏み出せない男の苦悩と、少しずつ脚本化されていくスーザンのノンフィクションの世界が映画の中で交互に描かれる。
つまりノンフィクションの映画化だけじゃなくて、脚本作るときの脚本家の苦悩というか思いっきりカウフマンの私的都合の部分まで映画化されてしまっている、という映画。
結構構成が複雑で、一つまた一つと異なる時間軸が合わさっていく。
僕は実話だと思って見ていた。だからスーザンもノンフィクションに登場する情熱的な蘭コレクタージョン・ラロシュも全て実在の人物だと思っていた。
そう思ってラストの展開を真に受けたら、この映画は最かなりの衝撃作になる。だから結構パニくった。
そうこうしているうちに映画が終わり、ぽけーっとエンドクレジットを見ていたらチャーリー・カウフマンの役者がニコラスケイジになっているじゃないか!
ニコラスケイジって言われたら、どっからどう見てもあいつはニコラスケイジにしか見えない。
なんで気づかなかったのだろう。アハハ
しかも帰ってから調べたら、弟のドナルド・カウフマンっていうのは架空の人物らしい。
となるとスーザンもジョン・ラロシュも架空の人物だったか。
そうだよな~。
スーザンが映画プロデューサーに映画化の話を持ちかけられたとき、スーザンは非常に喜びながら「でもあたし映画の脚本は書いたことないわ」と言う。
プロデューサーは「もう脚本家は決まっています」と答える。確か。
このシーンを見ている時点では、もう脚本も映画も完成して、観客は今この映画を"見て"いる。
だから、ああ、あなたのノンフィクションはこんなサイドストーリーでしか描かれない映画になっていますよ、すいませんっていう気持ちになる。
脚本家チャーリー・カウフマンはスーザンの写真で自慰をしてしまうわ、マンションを双眼鏡で覗き見したり、ストーキングしたり、スーザンを嘘つき呼ばわりするわで、見ているこっちが罪悪感にとらわれるし、こんなの描いていいのかと疑問に思っていたけど、全て創作ならば納得がいく。
いや!・・・がびーん!
今気になって調べたらスーザンもジョン・ラロシュも実在しており、ノンフィクション『蘭に魅せられた男―驚くべき蘭コレクターの世界』も全米で大反響を呼んだ本らしい。
えっ!えっ!まじ!
うーん、よくスーザンはOKしたなぁ。
この映画は前情報なしで事実関係も知らないまま見たほうが面白いかもな。ってここまで書いてから言うのも何だけど。
主人公が成長していく話なんてくだらない、カーチェイスなんかもいれたくない!って言っていた(脚本上わざと言わせた?)カウフマンが結局どういうストーリーを書いたのか(どういう目にあったか?)を楽しみに見るのもいいかもしれない。
どっからどこまでが、どの部分が事実なのか?を例え予備知識があっても巧みに目くらましをする。
全て事実だと思って見ていれば僕のように罪悪感に捕らえられたりびっくりしたりするだろうし、全て虚飾だと思って見ればそれはそれで違った感じ方もするだろう。
実際には事実と虚飾が入れ子になっている。
ストーリーはシンプルでいいんだ!ってカウフマンが映画の中で言っていた気がするが、事実もセリフも存在も原作もなにもかも1回以上否定する上、嘘と事実で複雑に入り組んだ構成を作り上げているが、でも結局この映画で表現していることはいたってシンプル。
このシンプルな主張を入り組んだ迷路(その迷路は複雑だけど誰でもゴールにたどり着く)のゴール地点に置く、ってなんていやらしいやつだ!って思うか、その遊び心ににやっとするか。
僕はこの映画面白かったけど少し疲労した。
僕は頭を出来るだけ使わないで済む映画が好きだから、頭を使うと疲れる。
ちなみにキャサリン・キーナーがちょびっと出ている。
カウフマンの恋人アメリア(カーラ・セイモア)がかわいい。
スーザン・オーリアン役にメリル・ストリープ。笑いとすれすれの女の怖さの演じ方が凄い。
ジョン・ラロシュ役にクリス・クーパー。
後は略。

映画のほうは、タランスキーというタランティーノとポランスキーを足して割ったような名前の映画監督が主人公。
あるきっかけで、監督作の主演にCG女優シモーヌを起用することになる。
CGだということがばれないか、薄氷を踏む思いの監督とは裏腹に、シモーヌの美貌と演技が大絶賛されることにより巻き起こるどたばたコメディー。
まあストーリーで面白く見れる。
悪戯に人生をかけるほど面白いことはないだろうな。悪戯っていってもばれても笑い飛ばせるようなものね。そこがむずい。
タランスキー(アルパチーノ)の妻役の女優がキャサリン・キーナー。
『リアルブロンド』で大人の30女をキュートに演じていた女優。
えっ!現在もう40過ぎてんじゃん。
マシュー・モディーンの恋人役だったのに今じゃアルパチーノの奥さん役か。
でも特に読みたいものもなくて、プロレス雑誌を読む。
それからふらふら物色していると、新井英樹『シュガー』の6巻があったので読む。
脳みそぐるぐる回転させながら思考と口が直結した天才少年の話。
『シュガー』読んで少し爽やかな気持ちになった後、また店内をふらふらする。
『いちご100%』という漫画があった。週間少年ジャンプに連載されていて、最近読み始めている。
この際1巻から読んでみようと思って読む。
そっか、いちごパンツから始まったからいちご100%なのか。
ありえないくらい可愛い女の子から、それも1人じゃなくて3人、いや4人から思いを寄せられウハウハの高校生が主人公。
学園恋愛物。
7巻まで読んでちょっとブルーになる。
つまんなかったわけじゃなくて、ありえねーって思いつつ結構つぼ突付いてくるからはまってしまった。そんな自分にブルーになる。
主人公っていうのが映画監督を夢見ている男の子なんだけど、運動神経がなく頭も悪いし容姿もそんなに良くない。
ただ、女の子に優しくて少し真面目なやつなんだな。
かっこいい男で女の子に持てまくる奴っていうのも作品中に出てくるのだけど、本当にかわいい女の子の心はみんな主人公が一人でかっさらう。
もてないやつがもてているって設定が、この理想のハーレム状態に自分も成れるのではないかと錯覚を起こすけど、現実においては奇跡的な夢でしかない。
高校生のときにもし読んだなら、多分俺は「よっしゃ!明日からenjoyだぜ!」と意気込んで登校し、その日に肩を落として帰宅するんだ!まぁちがいない!
とか、たとえ一時でも現実とのギャップを考えてしまうほどはまってしまった自分が悲しい深夜5時。
でも、どんな結果になるにしろ楽しくハッピーに生きたいものだ。若いっていいね。フレッシュ!
続けてこれも最近週間少年ジャンプで読み出した『BLEACH』を読む。
途中2冊どっかいっててなかったので話がよく分からなくなる。
最初は格闘漫画ってわけじゃなかったんだねぇ。
霊感の強い高校生がひょんなことから死神になって、悪霊と戦うって漫画。悪霊のひとつひとつにドラマが設定されていて4話くらいで一つのストーリーが完結する。で、なんだかんだで気づいたら死神同士で殺し合いする格闘漫画。
幽遊白書みたいだな。
朝の9時を回ったところで帰って寝る。ぐぴー。

放浪者が川で溺れる。男が一人命がけで飛び込み、放浪者を救う。
放浪者は命を救われた上、命を救ってくれたこのブルジョワ男性の家にお世話になる。
ブルジョワ男性の家にはその妻と女中が住んでいる。この3人と放浪者とは生きてきた世界が違う。
放浪者という異質の存在が家の中に割り込んでくることにより巻き起こるドラマ。
人を思いやる精神、助け合う精神の素晴らしさを教えてくれるハートフルドラマ。
・・・では全くないのだな。
髭ぼうぼうの放浪者が公園の木陰で黒い犬と優しく戯れていたり、命を救ってくれた男性からサイズぴったりの上等な服を買って貰ったり、飯を振舞われたり、さ。
って部分だけ取り出してみればやっぱり自由で純粋な心優しき放浪者とそんな彼に優しく接する紳士の温かい交流が描かれているんじゃない、と誤解を招きそうなところ。
全然違うから。
だってブルジョワは所詮ブルジョワなんだから浮浪者に親切にするのは高慢な偽善的ポーズでしかないし、浮浪者は所詮浮浪者で自由すぎて自由すぎて規律も礼儀もないんだから。
この映画は予測不能な展開に一瞬で無音の思考静止時間が作り出されたかと思えば、えー!って思わず笑ってしまう展開になったり、とにかく刺激的。
誰が下品で誰が上品か。人に対してどういう態度をとるのがいい人間なのか。いい人間、悪い人間ってなにか。どう生きれば人は幸せになるのか。人間的な生き方とはどんなものなのか。等々疑問を投げかけているというよりも、価値観が否定されながら放浪し続けている世界が粛然としてただある。
この映画、素晴らしいって言えばいいのかな。いや、やだな。
好きです、って言っておこう。

韓国映画史上破格の約12億円の巨費を投じて作成。しかもその後監督がSFXに不満を持ち、アメリカでさらに3億円を投じてCGをバージョンアップしたとのこと。
CGがこれまたちゃっちくて、重さが全くない上に怪獣の動きが安いゲームの怪獣のような動きをする。
登場人物が面白いくらいにプロトタイプで薄っぺらなのね。これがまた。
ヒロインも微妙にかわいくないし。
脚本も、なぜ?どういうこと?おい!、っていうのがてんこもり。
ああ、きっとテレビ放送用にカットされているのだな、うん。
出演者はアメリカ人じゃなくて韓国人にしてほしかったな。
吹き替え版だったというのもチープさに拍車をかける。
たぶんくだらない映画として笑って見るものだと思うのだけど、声に出して笑ってしまったのは以下のシーンのみ。
現れた怪獣を見て軍の高官は言った。
「あれより醜いのはうちの女房くらいだ」
って文で書くと全然面白くねー!
つっこむのが好きな人は見ればいいと思う。
