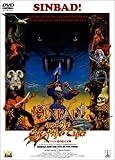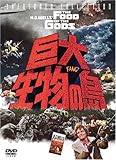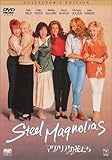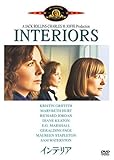でもまあいいや。調べてみたら「もう一度みたい!熱唱・感動の名場面」と題されて過去に放送したやつ流していたみたいだから。
そんでHDDレコーダーに録画してある過去の歌番組を整理していたら、7/13(火)放送の歌謡コンサートをまだ見ていなかった事に気づいて見た。
僕は神野美伽さんが嫌い。あの表情の豊かさと振り付けがどうしてもトラウマになる。
この放送で彼女は持ち歌「春夏秋冬 屋形船」を歌っていた。この曲は最近田川寿美さんが歌っていたので気になって聴いてみた。
この人は本当上手い。声の切り方等絶妙なのですね。映像を見ないで声だけ聞いたらファンになりそうな。
寿美さんで聴いたときはあまり印象に残っていない「春夏秋冬 屋形船」だがこんな名曲だったとは思わなかった。
(ちなみに改めて寿美版も聞いてみたけどこちらはこちらで流れるような艶のある歌い方でとても素晴らしい)
最初浴衣姿の坂本冬美と藤あや子と神野美伽の三人がそれぞれ持ち歌を一曲ずつ歌って、そのあとこの三人がまた一人ずつ今度は民謡を歌った。
初めて知ったけど藤さんは民謡出身だったのだな。
まず藤さんが「秋田音頭」を歌う。うまい。一声発した瞬間から世界が一瞬で転換されたような衝撃があった。
会場の空気が一瞬の内に藤さんの歌声でがらっと明るくなったと言えばわかりやすいか。
藤さんの演歌は少々飽き気味だったため期待していなかったのに新たな魅力はっけ~ん!演歌の時と民謡の時で声の張りが全然違うよ。
次に冬美さんが「よさこい鳴子踊り」を歌う。
確か冬美さんは復帰後に民謡の大家のもとに通ってレッスンを受けているとかいう話をどこかで聞いた。
こちらも坂本冬美だけあって聞き応えのある民謡だった。
最後に神野さんが「ソーラン節」。大いに盛り上がる。
以下個人的見解で
演歌:藤あや子<神野美伽<=坂本冬美
民謡:神野美伽<坂本冬美<=藤あや子
今回は三人だけ出演なのかと思ったら、いやいや、出ました、僕のお気に入りの林あさ美さんと城之内早苗さんが。
二人とも浴衣姿だった。歌も堪能。
さて、神野さんも戦慄でしたが一番戦慄だったのが、岩崎宏美さん。
この人はもう周知の通りめちゃくちゃ凄い歌手なのだけど、今回歌った名曲「聖母たちのララバイ」は特に名歌唱だった。
母性なのかな、聞き手を自然に歌で包み込んでしまうその歌唱はもう通常の歌手のレベルをはるかに超えている。
戦慄です。