2009年 監督:バフマン・ゴバディ
at ギンレイホール
『酔っぱらった馬の時間』という映画史上屈指の名作(だと思っている)イラン映画がある。
その監督がこのバフマン・ゴバディ。
と言いつつ『酔っぱらった馬の時間』しか見ていないのだけど、だからこそギンレイの予告編で突然バフマン・ゴバディという名前を見たときは本当びっくりして歓喜した。
予告編を見ると、西洋文化が規制されたイランで逮捕されたりしながらも好きな音楽をやり続ける若者達を追ったドキュメンタリーっぽい。
規制されている音楽を扱うわけだからテヘランでの撮影は無許可のゲリラ撮影。
ドキュメンタリーかぁと思いながらも、こんなに本気でギンレイに行くのを楽しみにしたのは久しぶりだ。
で、実際観てどうかというと、面白かったことは面白かったが見る前の期待値が高すぎたかもしれない。
ドキュメンタリーだと思っていたら、実在の事件人物に基づくというだけでドキュメンタリーでは無かった。
その点はよかったのだが、なにしろ音楽を扱っているわけだから半分以上音楽が流れて、ちょっと神経が疲れてしまった。
音楽のためならなんでもする便利屋のナデル(ハメッド・ベーダード)は息吸ってないんじゃないかと思うくらいのマシンガントークで、強烈で面白すぎるのだけどこれも一種の音楽のようなもの。
となると8割かた音楽が流れている感じか。
疲れる原因になった音楽だけど、実はどれもこれも本当に素晴らしい。
ジャンルも多岐に渡り、ロック、フォーク、ラップ、ブルース、ヘビメタ、伝統音楽を融合してプログレみたいなロック等々、なんでもありだ。
イランではこれらは全部音楽自体アンダーグラウンドになる。
あまり歌詞の字幕を読まなかったけど、歌詞だってイランの現状を訴えるものだったり、規制された社会での切実な夢を叫ぶものだったりする。
本当の自分がどうとか、そんな薄っぺらで内容の無い便所のネズミのクソにも匹敵するくだらない物の考え方を歌詞にしてしまう国とは違うのです。
上に貼っ付けた予告編で2,3曲聴ける。
特に印象に残ったのは現在イランで最も有名なラップミュージシャンとか、ボブ・ディランも真っ青の悪声のエンジニアのババクとか、主役のアシュカン&ネガルのインディーロックとか。
西洋音楽の音楽人口が少ないだけに玉石混交かと思いきや、音楽をやる環境が困難で切実なためジャンルを超えてどれもが本当に「ロック」という感じがする。
ただ、やはり音楽を聴きにきたわけじゃなくて映画を観に来たわけですよ。
映画としても面白いことは確かなんだけども、映画の中で使われる音楽がいかに破壊力を持つのかという事実を改めて認識するはめになってしまった。
2011年1月30日日曜日
映画『闇の列車、光の旅』
2009年 監督:キャリー・ジョージ・フクナガ
at ギンレイホール
![闇の列車、光の旅 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IFQ3zh%2BUL.jpg)
こえ~、まじこえ~。メキシコのギャング団。
渋谷のチーマーがままごとに思えてくる。
リーダーの男の顔面には全体に刺青が彫られていて、しかも右と左に大きく彫りこまれた「MS」の二文字はチーム名の頭文字だ。
もうこの顔はギャングというか頭の悪いギャグとしか思えないが、捕まえた敵対するチームの男を容赦なく銃殺した後ばらばらにして犬に喰わせるシーンを見てしまったら、「MS」の刺青を見ただけで震え上がってしまう。
そんな恐ろしいギャング組織に所属する青年カスペル(エドガル・フローレス)が主人公。
もう一人の主人公がサイラ(パウリナ・ガイタン)。
こちらはホンジュラスに住む女性で、子供の頃から離れ離れだった父親がアメリカから強制送還されて戻ってきたのを契機に、叔父を含めた3人でアメリカに渡ろうとしていた。
普通に行くんじゃなくて、つまりは不法移民。
なんの接点も無い二人だけど、カスペルが死を約束されるような考えるだに恐ろしいある裏切りをしたことで組織に追われ、逃げても無駄だと知りながらサイラ達アメリカを目指す移民集団に合流する。
中盤以降はロードムービーになる。
移民にしろ組織に追われるカスペルにしろ、ちょっと失敗すればあっけない最期が待ち受ける旅路。
カスペル役のエドガル・フローレスはこれが映画デビュー作らしいが、よく見つけてきたな。
役どころとして、まずなによりギャングであるから強くて悪そうであり、でも少年に慕われるいいお兄さんでもあり、過酷な環境で冷酷に大人びていながらも年相応の可愛らしさもあり、色気もあり、っていうのをエドガル・フローレスはそのままで全部体現しちゃっている。
演技がどうこうという前に役そのものだから。
と思わせてしまうくらいの演技だとしたらぶっ飛ぶけど。
アメリカ行きをしぶるサイラを叔父が「アメリカも厳しいと思うが ここよりはましだろう」と説得するシーンで、家のベランダなのか共同広場なのか分からないがとにかく丘の上から眼下にびっしり詰まった平屋を一望できる場所でそんなこと言われても、いやこんな眺めのいいところを離れるのはもったいないと思ってしまう。
眺めのいい家が一番です。(今度引っ越すときは丘の上に住もう)
そんなものより生活水準の低さの方がはるかに深刻だということなのだろうが。
あれ、予告編で少し映っているの見るとそれほどいい眺めでもないかも。
ギャングMS-13は実在する組織らしい。
Wiki
at ギンレイホール
![闇の列車、光の旅 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IFQ3zh%2BUL.jpg)
こえ~、まじこえ~。メキシコのギャング団。
渋谷のチーマーがままごとに思えてくる。
リーダーの男の顔面には全体に刺青が彫られていて、しかも右と左に大きく彫りこまれた「MS」の二文字はチーム名の頭文字だ。
もうこの顔はギャングというか頭の悪いギャグとしか思えないが、捕まえた敵対するチームの男を容赦なく銃殺した後ばらばらにして犬に喰わせるシーンを見てしまったら、「MS」の刺青を見ただけで震え上がってしまう。
そんな恐ろしいギャング組織に所属する青年カスペル(エドガル・フローレス)が主人公。
もう一人の主人公がサイラ(パウリナ・ガイタン)。
こちらはホンジュラスに住む女性で、子供の頃から離れ離れだった父親がアメリカから強制送還されて戻ってきたのを契機に、叔父を含めた3人でアメリカに渡ろうとしていた。
普通に行くんじゃなくて、つまりは不法移民。
なんの接点も無い二人だけど、カスペルが死を約束されるような考えるだに恐ろしいある裏切りをしたことで組織に追われ、逃げても無駄だと知りながらサイラ達アメリカを目指す移民集団に合流する。
中盤以降はロードムービーになる。
移民にしろ組織に追われるカスペルにしろ、ちょっと失敗すればあっけない最期が待ち受ける旅路。
カスペル役のエドガル・フローレスはこれが映画デビュー作らしいが、よく見つけてきたな。
役どころとして、まずなによりギャングであるから強くて悪そうであり、でも少年に慕われるいいお兄さんでもあり、過酷な環境で冷酷に大人びていながらも年相応の可愛らしさもあり、色気もあり、っていうのをエドガル・フローレスはそのままで全部体現しちゃっている。
演技がどうこうという前に役そのものだから。
と思わせてしまうくらいの演技だとしたらぶっ飛ぶけど。
アメリカ行きをしぶるサイラを叔父が「アメリカも厳しいと思うが ここよりはましだろう」と説得するシーンで、家のベランダなのか共同広場なのか分からないがとにかく丘の上から眼下にびっしり詰まった平屋を一望できる場所でそんなこと言われても、いやこんな眺めのいいところを離れるのはもったいないと思ってしまう。
眺めのいい家が一番です。(今度引っ越すときは丘の上に住もう)
そんなものより生活水準の低さの方がはるかに深刻だということなのだろうが。
あれ、予告編で少し映っているの見るとそれほどいい眺めでもないかも。
ギャングMS-13は実在する組織らしい。
Wiki
2011年1月27日木曜日
映画『探偵物語』
1983年 監督:根岸吉太郎
BS2 録画
![探偵物語 デジタル・リマスター版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QbphCquOL.jpg)
薬師丸ひろ子と松田優作の角川映画。
松田優作が探偵役でもべスパには乗らないしサスペンダーじゃないしアクションも無いし、同名のテレビドラマ『探偵物語』とは全く別物でドラマの映画化では無い。
という情報は知っていて、かつ小さい頃にテレビで見た気がしていたけど、もう全く見たことなかったや。
元妻が巻き込まれた殺人事件を追う探偵とそこに首を突っ込んでくる退屈な女子大生のお話。
殺人事件のサスペンスとはいえ、難解なトリックがあるわけでも無いし女子大生は重要な証拠を持ち去っちゃうし真犯人はあっさり自白するし警察は無能だし、でサスペンスという感じではなく、じゃあなんだと言うと"アイドル映画"だ。
ぽっちゃり薬師丸ひろ子の憎々しい溌剌さが可愛らしい。
可愛らしいといっても、おばちゃんが「あらぁお宅のお嬢さん可愛らしいわねぇ」と言いそうな可愛らしさで、要するにションベン臭いガキなんだ。
女子大生というか女子中学生のような。
薬師丸ひろ子の声が好きなんだけど、静寂を無神経にぐさぐさ引き裂いていく大きい声なんかもガキくさい。
一方松田優作の方は人生の辛酸をなめてきたどこか冴えない感じもする正に大人の男なのだ。
そんな大人の男がガキに好意を寄せるわけないと思いつつも、逆に汚れていない初々しさに惹かれるもんなのかなぁ。
成熟と初々しさの距離を縮めるのは濃厚なディープキス。
監督根岸吉太郎。
アイドル映画というとつまらないイメージしかないけど、これはよく撮れていてなかなか面白かった。
やっぱり長回しっていうのはいいなぁ。
根岸吉太郎はATGの『遠雷』しか見たことないと思っていたら、あまり面白くなかった『サイドカーに犬』もこの人だったか。
結構いろんな人が出ている。
財津一郎、岸田今日子、秋川リサ、林家木久蔵、ストロング金剛、荒井注、蟹江敬三、虹色の湖中村晃子、本牧で死んだ娘は鴎になったーよ~鹿内孝。
財津一郎は登場シーンとか白いスーツから透けて見える真っ赤なトランクスや赤い靴下など、コメディ的役回りだと思っていたけど、一応こわもてのやくざだったらしい。どうしてもちゃかしているようにしか見えないけどね。
薬師丸ひろ子が豪邸のリビングでエアロビの真似事しているところでふと思い出したけど、井筒の『晴れ、ときどき殺人』で渡辺典子がレオタード姿でエアロビしていたリビングもこんな感じのセットだった気がする。
『晴れ、ときどき殺人』は見た後即HDDレコーダーから削除したので確かめようがないが。
浜辺でアクセサリを売っているヒッピーの生き残りの風体が強烈だった。
いや、それよりも恐るべきは80年代ファッションか。
BS2 録画
![探偵物語 デジタル・リマスター版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QbphCquOL.jpg)
薬師丸ひろ子と松田優作の角川映画。
松田優作が探偵役でもべスパには乗らないしサスペンダーじゃないしアクションも無いし、同名のテレビドラマ『探偵物語』とは全く別物でドラマの映画化では無い。
という情報は知っていて、かつ小さい頃にテレビで見た気がしていたけど、もう全く見たことなかったや。
元妻が巻き込まれた殺人事件を追う探偵とそこに首を突っ込んでくる退屈な女子大生のお話。
殺人事件のサスペンスとはいえ、難解なトリックがあるわけでも無いし女子大生は重要な証拠を持ち去っちゃうし真犯人はあっさり自白するし警察は無能だし、でサスペンスという感じではなく、じゃあなんだと言うと"アイドル映画"だ。
ぽっちゃり薬師丸ひろ子の憎々しい溌剌さが可愛らしい。
可愛らしいといっても、おばちゃんが「あらぁお宅のお嬢さん可愛らしいわねぇ」と言いそうな可愛らしさで、要するにションベン臭いガキなんだ。
女子大生というか女子中学生のような。
薬師丸ひろ子の声が好きなんだけど、静寂を無神経にぐさぐさ引き裂いていく大きい声なんかもガキくさい。
一方松田優作の方は人生の辛酸をなめてきたどこか冴えない感じもする正に大人の男なのだ。
そんな大人の男がガキに好意を寄せるわけないと思いつつも、逆に汚れていない初々しさに惹かれるもんなのかなぁ。
成熟と初々しさの距離を縮めるのは濃厚なディープキス。
監督根岸吉太郎。
アイドル映画というとつまらないイメージしかないけど、これはよく撮れていてなかなか面白かった。
やっぱり長回しっていうのはいいなぁ。
根岸吉太郎はATGの『遠雷』しか見たことないと思っていたら、あまり面白くなかった『サイドカーに犬』もこの人だったか。
結構いろんな人が出ている。
財津一郎、岸田今日子、秋川リサ、林家木久蔵、ストロング金剛、荒井注、蟹江敬三、虹色の湖中村晃子、本牧で死んだ娘は鴎になったーよ~鹿内孝。
財津一郎は登場シーンとか白いスーツから透けて見える真っ赤なトランクスや赤い靴下など、コメディ的役回りだと思っていたけど、一応こわもてのやくざだったらしい。どうしてもちゃかしているようにしか見えないけどね。
薬師丸ひろ子が豪邸のリビングでエアロビの真似事しているところでふと思い出したけど、井筒の『晴れ、ときどき殺人』で渡辺典子がレオタード姿でエアロビしていたリビングもこんな感じのセットだった気がする。
『晴れ、ときどき殺人』は見た後即HDDレコーダーから削除したので確かめようがないが。
浜辺でアクセサリを売っているヒッピーの生き残りの風体が強烈だった。
いや、それよりも恐るべきは80年代ファッションか。
2011年1月22日土曜日
熊木杏里CONCERT 2011 東京国際フォーラム
1年ぶりくらいに行ってきた熊木杏里のライブ。
東京国際フォーラムのホールC。
3階の席で少し遠いがよく見渡せる。
バックライトの中、光に包まれて幻のように登場する等、今回は少しだけ演出が凝っていた。
登場すると深いお辞儀の後に無言のままピアノに向い、一曲目から弾き語り。
しかも大好きな曲『あなたに逢いたい』。
おお、しっとり感動だ。
ギター、ベース、キーボード、ドラムにチェロのバンド構成で始まる2曲目は、ずっとライブで聴きたいと思っていた『ノラ猫みたいに』で、イントロ聞いた瞬間に驚愕と歓喜に押しつぶされそうになりながらもベースの人の手拍子煽りもぶっち無視して(すいません)なんとか声に集中していた。
「悲しい約束は 叶わないほうがいい」の叶わないの「な」で声が裏返るところが好きなんだけど、やっぱりあれはレコード録音時だけのたまたまだったっぽい。
それにしても、ちょっと太ったのかな。。。
最初の二曲だけで大分満足してしまった。
『ノラ猫みたいに』に続いて三曲目『モウイチド』。
数少ないアップテンポの曲を連続でやっちゃって最初から全開だ。
MC後の4曲目以降はもう順番忘れた。
終演後にセットリストが張り出されるだろうと思っていたら、張り出されなかった。
どのみち携帯を家に置いてきたから撮れないけどさ。
以下、順不同で思い出す限り。
『新しい私になって』『センチメンタル』『ひみつ』『一千一秒』『雨が空から離れたら』『Snow』『君の名前』『おうちを忘れたカナリア』『ムーンスター』『君まではあともう少し』『最後の羅針盤』『春の風』
『バイバイ』
全体的に思ったのは、熊木杏里は最近調子悪いのかな。
ちょこちょこ音外して安定感が無かった。
裏声じゃない高音も少し乱暴な感じに聞こえる。スピーカーのせいか席の位置のせい?
弾き語りだと神がかって歌が上手くなるけど、弾き語りは1曲目とアンコールの最後の『バイバイ』だけだった。
ピアノ伴奏やギター伴奏のみのシンプルな構成の時も少し上手くなるが、これも数少ない。
数少ない上に舞台から照射される青いスポットライトが直撃してまぶしくてしょうがなかった。
一回弾き語りだけのライブを聞いてみたいなぁ。
3階の席だったので、上方から熊木杏里に当たるスポットライトが背後の床に影を落としているのが見えて、これが非常に美しかった。
楕円の光の輪の中に熊木杏里の上半身のシルエットが収まり、あの独特な右手の動きもそのまま影に投影されるから、楕円枠の幻想的にゆらめくポートレートを見ているようで。
ライブが終わって会場内で一服した後、グッズ売り場をうろついてみる。
初のライブDVDが販売されるらしいんだよね。
開演前にチェックしたときは長蛇の列ができていて、しかも在庫が少なくなってきたので今並んでいる人全員には行き渡らないかもしれないとアナウンスしていた。
でも終演後にも少し販売する、と。
どうせとっくに売り切れているんだろうと覗いてみると、人だかりはあるけど並んでいないしまだ販売している。
ど、どうしよう・・・入場時に貰ったチラシを見ると2枚組みで8500円もするんだよな。
2枚目なんかほとんどインタビューだけっぽいし。
それで8500円か。
ここでしか買えないなんてことはないだろうしamazonあたりで安くなるまで待とうか。
でも熊木杏里のブログくらいでしかこのDVDの発売の発表が無い事が非常に怪しい。店頭販売は無いのかもしれない。
ん?オリジナルサイン入りキーホルダー付き、か。。。
といってもライブ中に在庫を取り寄せるくらいだから直筆じゃないんだろうな。。。
迷ったけど今回のライブが少しだけ消化不良な面もあったので、えいっと買ってしまった。







東京国際フォーラムのホールC。
3階の席で少し遠いがよく見渡せる。
バックライトの中、光に包まれて幻のように登場する等、今回は少しだけ演出が凝っていた。
登場すると深いお辞儀の後に無言のままピアノに向い、一曲目から弾き語り。
しかも大好きな曲『あなたに逢いたい』。
おお、しっとり感動だ。
ギター、ベース、キーボード、ドラムにチェロのバンド構成で始まる2曲目は、ずっとライブで聴きたいと思っていた『ノラ猫みたいに』で、イントロ聞いた瞬間に驚愕と歓喜に押しつぶされそうになりながらもベースの人の手拍子煽りもぶっち無視して(すいません)なんとか声に集中していた。
「悲しい約束は 叶わないほうがいい」の叶わないの「な」で声が裏返るところが好きなんだけど、やっぱりあれはレコード録音時だけのたまたまだったっぽい。
それにしても、ちょっと太ったのかな。。。
最初の二曲だけで大分満足してしまった。
『ノラ猫みたいに』に続いて三曲目『モウイチド』。
数少ないアップテンポの曲を連続でやっちゃって最初から全開だ。
MC後の4曲目以降はもう順番忘れた。
終演後にセットリストが張り出されるだろうと思っていたら、張り出されなかった。
どのみち携帯を家に置いてきたから撮れないけどさ。
以下、順不同で思い出す限り。
『新しい私になって』『センチメンタル』『ひみつ』『一千一秒』『雨が空から離れたら』『Snow』『君の名前』『おうちを忘れたカナリア』『ムーンスター』『君まではあともう少し』『最後の羅針盤』『春の風』
『バイバイ』
全体的に思ったのは、熊木杏里は最近調子悪いのかな。
ちょこちょこ音外して安定感が無かった。
裏声じゃない高音も少し乱暴な感じに聞こえる。スピーカーのせいか席の位置のせい?
弾き語りだと神がかって歌が上手くなるけど、弾き語りは1曲目とアンコールの最後の『バイバイ』だけだった。
ピアノ伴奏やギター伴奏のみのシンプルな構成の時も少し上手くなるが、これも数少ない。
数少ない上に舞台から照射される青いスポットライトが直撃してまぶしくてしょうがなかった。
一回弾き語りだけのライブを聞いてみたいなぁ。
3階の席だったので、上方から熊木杏里に当たるスポットライトが背後の床に影を落としているのが見えて、これが非常に美しかった。
楕円の光の輪の中に熊木杏里の上半身のシルエットが収まり、あの独特な右手の動きもそのまま影に投影されるから、楕円枠の幻想的にゆらめくポートレートを見ているようで。
ライブが終わって会場内で一服した後、グッズ売り場をうろついてみる。
初のライブDVDが販売されるらしいんだよね。
開演前にチェックしたときは長蛇の列ができていて、しかも在庫が少なくなってきたので今並んでいる人全員には行き渡らないかもしれないとアナウンスしていた。
でも終演後にも少し販売する、と。
どうせとっくに売り切れているんだろうと覗いてみると、人だかりはあるけど並んでいないしまだ販売している。
ど、どうしよう・・・入場時に貰ったチラシを見ると2枚組みで8500円もするんだよな。
2枚目なんかほとんどインタビューだけっぽいし。
それで8500円か。
ここでしか買えないなんてことはないだろうしamazonあたりで安くなるまで待とうか。
でも熊木杏里のブログくらいでしかこのDVDの発売の発表が無い事が非常に怪しい。店頭販売は無いのかもしれない。
ん?オリジナルサイン入りキーホルダー付き、か。。。
といってもライブ中に在庫を取り寄せるくらいだから直筆じゃないんだろうな。。。
迷ったけど今回のライブが少しだけ消化不良な面もあったので、えいっと買ってしまった。







2011年1月19日水曜日
映画『アフガン零年』
2003年 監督:セディク・バルマク
BS2 録画
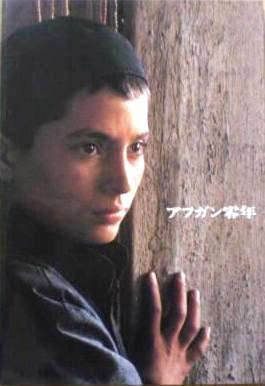
同時多発テロ、アフガニスタン紛争の記憶も新しい頃に公開され、公開当時話題になっていた映画。
アフガン復興後の第一作目らしい。
中央アジアや中東で製作された映画にはずれはないから面白いはずだけど、なんとなく敬遠して今まで何度かNHKで放映していたけど録画しなかった映画をやっと見る。
ドキュメンタリーのように始まるからドキュメンタリーなんだっけと思うが、ドキュメンタリーにしてはカットもセリフのタイミングもよくできているなぁ、と思っているとやっぱりドキュメンタリーじゃ無かった。
とするとデモとかタリバン批判とかアフガニスタンでよく撮影したものだ。
と思ったらアフガニスタン紛争で一応タリバン政権は崩壊しているんだね。(知らないにも程があるか)
そりゃあタリバン政権化でこれは撮影できるわけないか。
それでもタリバン自体はまだ活発に活動しているから危険だっただろう。
役者は皆素人らしい。
主演の少女が凄い。
まっすぐな眼差しくらいなら普通に演技で出来るもんだと思うけど、その射すような強く純粋な眼差しに怯えと悲しみを湛えることは演技じゃできないだろう。
少女が泣くと本気で悲しい。
「なんとこの子はまるで・・・この子はまるで天使のようだ」
とタリバンのロリコン爺さんに言わしめた美しき少女の顔が悲しみと恐怖で歪む時、少女やアフガニスタンの紛争と貧困の歴史が痛いくらいに突き刺さってくる。
ストーリーは一家の男性を戦争などで全て失った女だけの家族が、貧困にあえいだ末に少女に男の格好をさせて働きに出すというもの。
伊達や酔狂で少女に男の格好をさせているんじゃない。
男でないとろくに外も出れないし働けもしない。
しかも男装がタリバンにばれたら死刑という命がけ。
『花ざかりの君たちへ』みたいな暢気な国の暢気なお遊びじゃないんですよ、全く。
いい奴だった"お香や"を始め、イケメン少年達に囲まれてはいたけどさ。
縄跳びで無邪気に遊ぶことすらできない少女の物語。
題材も衝撃的だけど、なにより映画の質が極めて高いので82分と短いながらも濃密に堪能できる作品。
BS2 録画
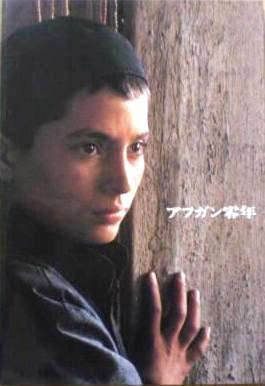
同時多発テロ、アフガニスタン紛争の記憶も新しい頃に公開され、公開当時話題になっていた映画。
アフガン復興後の第一作目らしい。
中央アジアや中東で製作された映画にはずれはないから面白いはずだけど、なんとなく敬遠して今まで何度かNHKで放映していたけど録画しなかった映画をやっと見る。
ドキュメンタリーのように始まるからドキュメンタリーなんだっけと思うが、ドキュメンタリーにしてはカットもセリフのタイミングもよくできているなぁ、と思っているとやっぱりドキュメンタリーじゃ無かった。
とするとデモとかタリバン批判とかアフガニスタンでよく撮影したものだ。
と思ったらアフガニスタン紛争で一応タリバン政権は崩壊しているんだね。(知らないにも程があるか)
そりゃあタリバン政権化でこれは撮影できるわけないか。
それでもタリバン自体はまだ活発に活動しているから危険だっただろう。
役者は皆素人らしい。
主演の少女が凄い。
まっすぐな眼差しくらいなら普通に演技で出来るもんだと思うけど、その射すような強く純粋な眼差しに怯えと悲しみを湛えることは演技じゃできないだろう。
少女が泣くと本気で悲しい。
「なんとこの子はまるで・・・この子はまるで天使のようだ」
とタリバンのロリコン爺さんに言わしめた美しき少女の顔が悲しみと恐怖で歪む時、少女やアフガニスタンの紛争と貧困の歴史が痛いくらいに突き刺さってくる。
ストーリーは一家の男性を戦争などで全て失った女だけの家族が、貧困にあえいだ末に少女に男の格好をさせて働きに出すというもの。
伊達や酔狂で少女に男の格好をさせているんじゃない。
男でないとろくに外も出れないし働けもしない。
しかも男装がタリバンにばれたら死刑という命がけ。
『花ざかりの君たちへ』みたいな暢気な国の暢気なお遊びじゃないんですよ、全く。
いい奴だった"お香や"を始め、イケメン少年達に囲まれてはいたけどさ。
縄跳びで無邪気に遊ぶことすらできない少女の物語。
題材も衝撃的だけど、なにより映画の質が極めて高いので82分と短いながらも濃密に堪能できる作品。
2011年1月16日日曜日
映画『ルンバ!』
2008年 監督:ドミニク・アベル、他
at ギンレイホール
迷ったが怖いもの見たさのような気持ちで結局見てしまった。
結論として、やっぱり僕には合わない。
先週見た『アイスバーグ!』でもう分りきっていたじゃないかと自分を叱責しながらの長い77分。
やっぱりギャグが異常なまでにつまらない。
映像として面白いところがあったのかもしれないけど、とにかくギャグがいらっとするのでそれどころじゃない。
少なくとも、火事でドアだけが残った家で壁も無いのに律儀にドアを開けて出入りするギャグ?なんて、『キシュ島の物語』でモフセン・マフマルバフがドアをどう撮影したかを見れば、この『ルンバ!』がいかにつまらないか分かるだろう、、、と思う。(※映画のスタイルの違いは問題じゃない)
ただ、なんか頭から離れないんだよなぁ。ちきしょう。
影だけがダンスするシーンはどう撮影したんだろう?
影だけで見るとフィオナ・ゴードンのプロポーションは奇跡的に素晴らしいなと思ってぼーっとしていると澱みなく本来の影に戻るから少し驚いた。
本来の影に戻った後、実体と影との動きに少しずれがあった気がするから、影だけ撮影したものを壁に投射していたのかな。
主要な役者は前作と同じで、監督の二人はもとより『アイスバーグ!』の船長さんも出演している。またもやセリフ無しで。
『アイスバーグ!』とつなげてみると、この夫婦二人はお互いパートナーよりも船長さんが大好きなんだね。
さんざん踊りを見せられたからどうせならラストも踊れよと念じていたが踊らず。
そういう消化不良も記憶に残る。
at ギンレイホール
迷ったが怖いもの見たさのような気持ちで結局見てしまった。
結論として、やっぱり僕には合わない。
先週見た『アイスバーグ!』でもう分りきっていたじゃないかと自分を叱責しながらの長い77分。
やっぱりギャグが異常なまでにつまらない。
映像として面白いところがあったのかもしれないけど、とにかくギャグがいらっとするのでそれどころじゃない。
少なくとも、火事でドアだけが残った家で壁も無いのに律儀にドアを開けて出入りするギャグ?なんて、『キシュ島の物語』でモフセン・マフマルバフがドアをどう撮影したかを見れば、この『ルンバ!』がいかにつまらないか分かるだろう、、、と思う。(※映画のスタイルの違いは問題じゃない)
ただ、なんか頭から離れないんだよなぁ。ちきしょう。
影だけがダンスするシーンはどう撮影したんだろう?
影だけで見るとフィオナ・ゴードンのプロポーションは奇跡的に素晴らしいなと思ってぼーっとしていると澱みなく本来の影に戻るから少し驚いた。
本来の影に戻った後、実体と影との動きに少しずれがあった気がするから、影だけ撮影したものを壁に投射していたのかな。
主要な役者は前作と同じで、監督の二人はもとより『アイスバーグ!』の船長さんも出演している。またもやセリフ無しで。
『アイスバーグ!』とつなげてみると、この夫婦二人はお互いパートナーよりも船長さんが大好きなんだね。
さんざん踊りを見せられたからどうせならラストも踊れよと念じていたが踊らず。
そういう消化不良も記憶に残る。
映画『ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士』
2009年 監督:ダニエル・アルフレッドソン
at ギンレイホール
![ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gjZRZaGJL.jpg)
二部のラストから継続するような形で三部が始まる。
二部でさわりに触れたリスベット(ノオミ・ラパス)の過去に蠢く国家の暗部がいよいよその実体を現し、リスベットとその周囲を巻き込みながら法廷での最終決戦の場へと怒涛のごとくに流れ込んでいく。
身動きの取れない眠れるリスベットに代わり奮闘するのは、円卓の騎士ならぬ狂卓の騎士達。3,4人くらいしかいなけど。
狂卓の騎士はもちろんミカエル(ミカエル・ニクヴィスト)が中心だが、値千金の大活躍をするのがリスベットのハッカー仲間の疫病神ことプレイグで、今まで部屋の中にしかいなかったのになんと外に出ているんだぜ。
びくびくした感じとその友情が感動的だ。
メールの送り主を特定するミカエルからの依頼もほっぽいてリスベットの依頼を最優先するのです。
リスベットが全ての忌まわしき過去にけりを付けるべく向かう正装は進化の最終形態のようなとびっきりのパンクスタイル。
いかすぜ。
一番好きだったのは独房に戻ったリスベットが顔を洗ってメイクを落とすところで、ど派手なスタイルの裏に隠れたか弱さが垣間見えるシーン。
148分もあるのでちょっと疲れたかな。
登場人物の名前を覚えようと字幕に釘付けになっていたら今度は顔を覚えられなかった。
結局ほとんど字幕ばかり見ていた気もする。
ただ、思わずいろんな口調が混ざって変な文章になるくらいいかしていて面白かったのは確かだぜぃ。
たぶん小説はもっと面白いんだろうな。
原作のスティーグ・ラーソンは惜しくも他界してしまったので続編はもう無いが、第5部までの構想があったらしい。
3部で完結した感じだが続きがあるとしたらどういう展開していたのか気になるところ。
at ギンレイホール
![ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gjZRZaGJL.jpg)
二部のラストから継続するような形で三部が始まる。
二部でさわりに触れたリスベット(ノオミ・ラパス)の過去に蠢く国家の暗部がいよいよその実体を現し、リスベットとその周囲を巻き込みながら法廷での最終決戦の場へと怒涛のごとくに流れ込んでいく。
身動きの取れない眠れるリスベットに代わり奮闘するのは、円卓の騎士ならぬ狂卓の騎士達。3,4人くらいしかいなけど。
狂卓の騎士はもちろんミカエル(ミカエル・ニクヴィスト)が中心だが、値千金の大活躍をするのがリスベットのハッカー仲間の疫病神ことプレイグで、今まで部屋の中にしかいなかったのになんと外に出ているんだぜ。
びくびくした感じとその友情が感動的だ。
メールの送り主を特定するミカエルからの依頼もほっぽいてリスベットの依頼を最優先するのです。
リスベットが全ての忌まわしき過去にけりを付けるべく向かう正装は進化の最終形態のようなとびっきりのパンクスタイル。
いかすぜ。
一番好きだったのは独房に戻ったリスベットが顔を洗ってメイクを落とすところで、ど派手なスタイルの裏に隠れたか弱さが垣間見えるシーン。
148分もあるのでちょっと疲れたかな。
登場人物の名前を覚えようと字幕に釘付けになっていたら今度は顔を覚えられなかった。
結局ほとんど字幕ばかり見ていた気もする。
ただ、思わずいろんな口調が混ざって変な文章になるくらいいかしていて面白かったのは確かだぜぃ。
たぶん小説はもっと面白いんだろうな。
原作のスティーグ・ラーソンは惜しくも他界してしまったので続編はもう無いが、第5部までの構想があったらしい。
3部で完結した感じだが続きがあるとしたらどういう展開していたのか気になるところ。
2011年1月13日木曜日
映画『サイコ』
1960年 監督:アルフレッド・ヒッチコック
BS2 録画
![サイコ (1960) ― コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ST028FM7L.jpg)
クレジットタイトルかっこいいな。
音楽といい、スタイリッシュさといい、ばらばらに切り刻まれているような不穏さといい。
ソウル・バス。ソウル市内バスの事ではない。タイトルデザイン:ソウル・バスとなっている。
この人はグラフィックデザイナーで、映画のタイトルデザインの第一人者として活躍し、映画に詳しい人なら当然知っている名前、っぽいな。
映画にタイトルデザインなんて分野があることすら知らなかったが、あの衝撃的にかっこいい『めまい』のタイトルデザインもソウル・バスだ。
『サイコ』は有名なシャワーシーンは部分的に見たことあるけど、全体的にどういう話かはそういえば知らない。
クレジットタイトル後のかったるい恋人同士の逢引きシーンやらマリオン(ジャネット・リー)がしでかす事件など、あのシャワーシーンに繋がる要素が全く無いから戸惑う。
まあそれはいいとして、この映画、そこらのホラー映画より恐ろしい。
巧みな演出で途切れることない通奏低音のように流れる緊迫感や不穏な空気が、ゆるやかにまたは突如に波打つから。
シャワーシーンもそうだし、人のよさそうな青年ノーマン(アンソニー・パーキンス)が母親の話で怒りを込めて身を乗り出す変化も怖い。
見るな!気付くな!で連続する緊迫感。
見る、こっそり見る、見られる、見ていないのに見た気になる、等々の印象的な視線の錯綜と、振り返る、舞い戻る等の180度の回転運動の組み合わせが怖さや面白さのポイントかな。
マリオンだけで見ても、デスクに腰掛けた成金男に間近で凝視され、早退して家にいるはずなのに路上で勤め先の社長に振り返り見られ、明らかに挙動不審に警官を見つめ、警官のくせに無表情で怪しい男のサングラスごしの視線は執拗なまでにマリオンを追いかけ、モーテルでは覗き穴からノーマンに見られ、惨殺な場面を一切見ていないのに恐怖とともに見た気になり、水を螺旋状に飲み込む排水溝の黒い穴は機能を停止して何も見ることができなくなった楕円の片目へと変換される。
180度の回転運動も様々な形で現れるのだが、その多くは死と連動している。
殺される奴は皆どこかに戻ろうとしていたし、階段を上るアーボガストは不安定で滑らかな飛躍をするカメラにより階段を下りるときが死の道行きとなり、簡単に予測は付くがそれでも恐ろしい回転して現れる母親の真実、殺人犯の回転するように切り替わる心の一方は死だし。
女優達の演技が少し微妙な気もし、ちょっと話しただけで全て分ったようなしたり顔で喋る男には何なんだよお前と突っ込みつつも、面白かった。
BS2 録画
![サイコ (1960) ― コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ST028FM7L.jpg)
クレジットタイトルかっこいいな。
音楽といい、スタイリッシュさといい、ばらばらに切り刻まれているような不穏さといい。
ソウル・バス。ソウル市内バスの事ではない。タイトルデザイン:ソウル・バスとなっている。
この人はグラフィックデザイナーで、映画のタイトルデザインの第一人者として活躍し、映画に詳しい人なら当然知っている名前、っぽいな。
映画にタイトルデザインなんて分野があることすら知らなかったが、あの衝撃的にかっこいい『めまい』のタイトルデザインもソウル・バスだ。
『サイコ』は有名なシャワーシーンは部分的に見たことあるけど、全体的にどういう話かはそういえば知らない。
クレジットタイトル後のかったるい恋人同士の逢引きシーンやらマリオン(ジャネット・リー)がしでかす事件など、あのシャワーシーンに繋がる要素が全く無いから戸惑う。
まあそれはいいとして、この映画、そこらのホラー映画より恐ろしい。
巧みな演出で途切れることない通奏低音のように流れる緊迫感や不穏な空気が、ゆるやかにまたは突如に波打つから。
シャワーシーンもそうだし、人のよさそうな青年ノーマン(アンソニー・パーキンス)が母親の話で怒りを込めて身を乗り出す変化も怖い。
見るな!気付くな!で連続する緊迫感。
見る、こっそり見る、見られる、見ていないのに見た気になる、等々の印象的な視線の錯綜と、振り返る、舞い戻る等の180度の回転運動の組み合わせが怖さや面白さのポイントかな。
マリオンだけで見ても、デスクに腰掛けた成金男に間近で凝視され、早退して家にいるはずなのに路上で勤め先の社長に振り返り見られ、明らかに挙動不審に警官を見つめ、警官のくせに無表情で怪しい男のサングラスごしの視線は執拗なまでにマリオンを追いかけ、モーテルでは覗き穴からノーマンに見られ、惨殺な場面を一切見ていないのに恐怖とともに見た気になり、水を螺旋状に飲み込む排水溝の黒い穴は機能を停止して何も見ることができなくなった楕円の片目へと変換される。
180度の回転運動も様々な形で現れるのだが、その多くは死と連動している。
殺される奴は皆どこかに戻ろうとしていたし、階段を上るアーボガストは不安定で滑らかな飛躍をするカメラにより階段を下りるときが死の道行きとなり、簡単に予測は付くがそれでも恐ろしい回転して現れる母親の真実、殺人犯の回転するように切り替わる心の一方は死だし。
女優達の演技が少し微妙な気もし、ちょっと話しただけで全て分ったようなしたり顔で喋る男には何なんだよお前と突っ込みつつも、面白かった。
2011年1月10日月曜日
映画『2001年宇宙の旅』
1968年 監督:スタンリー・キューブリック
BS2 録画
![2001年宇宙の旅 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZVSEIcELL.jpg)
初めてビデオテープに録画したのが学生の頃だから、10年以上前からいつでも見れる状態だった映画をやっと観る。
広い荒野で夕日のシルエットに猿の影が浮かぶが、動きがなんか人間が猿の真似をしているような不自然さがある。
どうやら着ぐるみを着ている人間らしい。
よくできた特殊メイクだ。
他の本物の動物達と段々違和感が無くなって溶け込んでくる。
それにしても宇宙のSFだと思っていたのに荒野で猿人達がウキーって吠えているのだが。。。
しかし神秘的な謎の石版が突如現れ、それに触れた猿人は道具を使用することを覚える。
ツァラトゥストラはかく語りきの音楽に乗せた仰々しい人類の夜明けシーンに笑いつつもなんかSFっぽくなってきたぞ、と思って観ていると、猿人が上空に投げた骨から突如シーンはスペースシャトルが飛ぶ宇宙へ切り替わる。
なんという時間の飛翔だ。
数十万、数百万年の跳躍は勢い余って2001年に行ってしまう。誤差の範囲だ。
ねっころがって観ていたら美しき青きドナウなんて聞かされるもんだから爆睡してしまった。
この音楽は無いわ~。
映画館で見なくてよかった。
巻き戻して再開。
再開後は意外とめりこんで見る。
冒頭50分くらいは序章に過ぎなかった。
ディスカバリー号の木星探査の章が始まってから俄然面白くなってくる。
かったるい音楽がほとんど無くなったからかな。
宇宙が黒い。当たり前だが黒い。
時間も空間も分らなくなりそうなどこまでも永遠に沈み込んで行く黒の質感が、白い宇宙船や黄色い宇宙服を異空間が混在しているかのように拒絶したり音も無く飲み込んだりしていく。
黒の中の白がよく映えるんだこれが。
ディスカバリー号の外見の緻密さと重そうな質感は圧巻だ。(白い作業用ポッドの造形もかっこいい)
黒と白を基調にしてぽつんと配色される赤や黄色の原色、無限の闇の中での永遠の静止を基本とした動き等々、ストイックなまでに必要最小限のものしか存在していない。
無駄なものがそぎ落とされすぎて余白みたいなものがなくなってくると却って息苦しくなるものだが、そもそも基調となっている黒と白は余白の色だ。
しかもどこまでも深く清潔な黒と白。
単調になりそうになると他の色がさりげなくアクセントを加える。
だから黒の深度に身を投じたまま、静かに沈み込んでいったり浮き上がったり、白のまばゆさにはっとして弾き出されたり、冷徹に研ぎ澄まされた無機的な闇の階層の内と外をゆらゆらとたゆたうことになる。
寒々としているのにどこか大きい温もりを持つ揺らぎに神経が麻痺してくる。
極めつけはラストで、映像といいストーリーといい、呆気にとられてしまった。
堰を切ったようにあふれ出す光の奔流から始まり、静寂の異空間までの10数分、息を呑んで見守ったものの、圧倒的な映像という感じではない。
トリップする準備はこれまでの2時間で十分すぎるほど整っているので、ここらで一発圧倒的な光の洪水をどうだといわんばかりに見せ付けたら簡単にトリップするだろう。
てもそんなもの見せてもドラッグきめたヒッピーが喜ぶだけだしね。
光の洪水のスピードに流されながらもボウマンの恐ろしく歪んだ顔のストップ画を挿入して抜きを入れたりして抑制するところはこれまでの演出と変わらない。
分りやすい光の洪水の余韻を引きずりながら、続く光の不定形に揺らぐ姿態のシーンも長いし。
だから「圧倒的」じゃないのだけど、じゃあ何なんだよと言われると、さっきから「圧倒的」だった・・・って言ってしまいそうになる語彙の無さに泣けてくる。
この映画で時間も空間も超越して平然と並列されている、例えば生と死、静と動、無機的有機的、肉体と精神(AI)、ミクロとマクロ、この世と反転してすぐ裏にあるあの世等々、まあイメージ次第なのだが、こういう反義要素が耳鳴りのような音楽とスピード感に比して恐ろしく静寂なあの木星突入の映像で一気に、大手を振って膨れ上がるわけだ。
闇に沈み込んでいく恐怖から一転して一分の隙間もない光の間隙に落ち込んでいく不安と、ネガポジ反転の気味悪さを伴いつつ。
それがつまり圧倒的。。。
簡単に言うと、面白かった。
1968年だもんな。当時に見たらもっと別の映像衝撃を受けたのだろうな。
ストーリーが不可解なのでそれが納得できなければWikipediaの解説を解釈の手引きとして見るのもいい。
昔はWikipediaに映画作品の解説なんて載っていなかった気がするが最近は充実しているんだねぇ。
全部読んでないけどへぇーと思ったのは、ヘルメット無しで真空に出ても「短時間であれば科学的に可能と考えられている」らしい。
そうか、あのシーンはおいおいと思ったけど、おいおいは僕の方でしたか。
BS2 録画
![2001年宇宙の旅 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZVSEIcELL.jpg)
初めてビデオテープに録画したのが学生の頃だから、10年以上前からいつでも見れる状態だった映画をやっと観る。
広い荒野で夕日のシルエットに猿の影が浮かぶが、動きがなんか人間が猿の真似をしているような不自然さがある。
どうやら着ぐるみを着ている人間らしい。
よくできた特殊メイクだ。
他の本物の動物達と段々違和感が無くなって溶け込んでくる。
それにしても宇宙のSFだと思っていたのに荒野で猿人達がウキーって吠えているのだが。。。
しかし神秘的な謎の石版が突如現れ、それに触れた猿人は道具を使用することを覚える。
ツァラトゥストラはかく語りきの音楽に乗せた仰々しい人類の夜明けシーンに笑いつつもなんかSFっぽくなってきたぞ、と思って観ていると、猿人が上空に投げた骨から突如シーンはスペースシャトルが飛ぶ宇宙へ切り替わる。
なんという時間の飛翔だ。
数十万、数百万年の跳躍は勢い余って2001年に行ってしまう。誤差の範囲だ。
ねっころがって観ていたら美しき青きドナウなんて聞かされるもんだから爆睡してしまった。
この音楽は無いわ~。
映画館で見なくてよかった。
巻き戻して再開。
再開後は意外とめりこんで見る。
冒頭50分くらいは序章に過ぎなかった。
ディスカバリー号の木星探査の章が始まってから俄然面白くなってくる。
かったるい音楽がほとんど無くなったからかな。
宇宙が黒い。当たり前だが黒い。
時間も空間も分らなくなりそうなどこまでも永遠に沈み込んで行く黒の質感が、白い宇宙船や黄色い宇宙服を異空間が混在しているかのように拒絶したり音も無く飲み込んだりしていく。
黒の中の白がよく映えるんだこれが。
ディスカバリー号の外見の緻密さと重そうな質感は圧巻だ。(白い作業用ポッドの造形もかっこいい)
黒と白を基調にしてぽつんと配色される赤や黄色の原色、無限の闇の中での永遠の静止を基本とした動き等々、ストイックなまでに必要最小限のものしか存在していない。
無駄なものがそぎ落とされすぎて余白みたいなものがなくなってくると却って息苦しくなるものだが、そもそも基調となっている黒と白は余白の色だ。
しかもどこまでも深く清潔な黒と白。
単調になりそうになると他の色がさりげなくアクセントを加える。
だから黒の深度に身を投じたまま、静かに沈み込んでいったり浮き上がったり、白のまばゆさにはっとして弾き出されたり、冷徹に研ぎ澄まされた無機的な闇の階層の内と外をゆらゆらとたゆたうことになる。
寒々としているのにどこか大きい温もりを持つ揺らぎに神経が麻痺してくる。
極めつけはラストで、映像といいストーリーといい、呆気にとられてしまった。
堰を切ったようにあふれ出す光の奔流から始まり、静寂の異空間までの10数分、息を呑んで見守ったものの、圧倒的な映像という感じではない。
トリップする準備はこれまでの2時間で十分すぎるほど整っているので、ここらで一発圧倒的な光の洪水をどうだといわんばかりに見せ付けたら簡単にトリップするだろう。
てもそんなもの見せてもドラッグきめたヒッピーが喜ぶだけだしね。
光の洪水のスピードに流されながらもボウマンの恐ろしく歪んだ顔のストップ画を挿入して抜きを入れたりして抑制するところはこれまでの演出と変わらない。
分りやすい光の洪水の余韻を引きずりながら、続く光の不定形に揺らぐ姿態のシーンも長いし。
だから「圧倒的」じゃないのだけど、じゃあ何なんだよと言われると、さっきから「圧倒的」だった・・・って言ってしまいそうになる語彙の無さに泣けてくる。
この映画で時間も空間も超越して平然と並列されている、例えば生と死、静と動、無機的有機的、肉体と精神(AI)、ミクロとマクロ、この世と反転してすぐ裏にあるあの世等々、まあイメージ次第なのだが、こういう反義要素が耳鳴りのような音楽とスピード感に比して恐ろしく静寂なあの木星突入の映像で一気に、大手を振って膨れ上がるわけだ。
闇に沈み込んでいく恐怖から一転して一分の隙間もない光の間隙に落ち込んでいく不安と、ネガポジ反転の気味悪さを伴いつつ。
それがつまり圧倒的。。。
簡単に言うと、面白かった。
1968年だもんな。当時に見たらもっと別の映像衝撃を受けたのだろうな。
ストーリーが不可解なのでそれが納得できなければWikipediaの解説を解釈の手引きとして見るのもいい。
昔はWikipediaに映画作品の解説なんて載っていなかった気がするが最近は充実しているんだねぇ。
全部読んでないけどへぇーと思ったのは、ヘルメット無しで真空に出ても「短時間であれば科学的に可能と考えられている」らしい。
そうか、あのシーンはおいおいと思ったけど、おいおいは僕の方でしたか。
1月INFO
- BShi 1月10日(月) 午後3:00~5:13
- 魂のジュリエッタ 1965年・イタリア/フランス
〔監督・原案・脚本〕フェデリコ・フェリーニ - BShi 1月10日(月) 午後10:05~11:48
- あゝ結婚 1964年・イタリア/フランス
〔監督〕ビットリオ・デ・シーカ - BS2 1月11日(火) 午前0:10~3:00(10日深夜)
- エレニの旅 2004年・ギリシャ/フランス/イタリア/ドイツ
〔監督・脚本〕テオ・アンゲロプロス - BShi 1月11日(火) 午後10:05~11:54
- ひまわり 1970年・イタリア
〔監督〕ビットリオ・デ・シーカ - BS2 1月12日(水) 午前0:15~2:36(11日深夜)
- シテール島への船出 1984年・ギリシャ/西ドイツ/イギリス/イタリア
〔製作・監督・脚本〕テオ・アンゲロプロス - BS2 1月13日(木) 午前0:45~2:59(12日深夜)
- 永遠と一日 1998年・ギリシャ/フランス/イタリア
〔製作・監督・脚本〕テオ・アンゲロプロス - BS2 1月14日(金) 午前0:45~2:51(13日深夜)
- 霧の中の風景 1988年・ギリシャ/フランス
〔製作・監督・原案・脚本〕テオ・アンゲロプロス - BS2 1月18日(火) 午前0:50~2:22 (17日深夜)
- 紳士は金髪がお好き 1953年・アメリカ
〔監督〕ハワード・ホークス - BS2 1月19日(水) 午前0:41~2:57 (18日深夜)
- 翼よ!あれが巴里の灯だ 1957年・アメリカ
〔監督・脚本〕ビリー・ワイルダー - BS2 1月20日(木)午前0:45~2:56(19日深夜)
- フェイシズ 1968年・アメリカ
〔監督・脚本〕ジョン・カサベテス - BS2 1月24日(月) 午後9:00~10:52
- 探偵物語 1983年・日本
〔監督〕根岸吉太郎 - BS2 1月25日(火) 午後9:00~10:53
- セーラー服と機関銃 1981年・日本
〔監督〕相米慎二 - BS2 1月26日(水) 午後9:00~10:50
- Wの悲劇 1984年・日本
〔監督・脚本〕澤井信一郎 - BS2 1月28日(金) 午前0:45~2:45(27日深夜)
- メトロポリス 1927年・ドイツ
〔監督〕フリッツ・ラング
新年なのでいわゆる名作が目白押し。
上旬にフェリーニ特集があって8日の『若者のすべて』だけ録画しようとしていたら忘れてしまった。
アンゲロプロス祭りがまたやってくる。
こないだ放映していたときのアナログ録画はちょうどまだ観ていなかったので今度はいい画質で録画しよう。
薬師丸ひろ子特集のおかげで久しぶりに相米慎二が観れる。
メトロポリスは楽しみだなぁ。
2011年1月9日日曜日
映画『ミレニアム2 火と戯れる女』
2009年 監督:ダニエル・アルフレッドソン
at ギンレイホール
![ミレニアム2 火と戯れる女 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/514pPyUpnJL._SL160_.jpg)
ミレニアム3部作の2作目。
130分もあるから覚悟していたけど、見終わったら「あれっもう終わってしまった」という感じ。
エンドロール中に振り返ってみるといろんなシーンが思い出されて確かに130分のボリュームがあったと納得する。
前作を見ていないと何がなんだか分らない点も結構あるだろうな。
私はサディストの豚ですとか。
ミカエルとリスベットがそれぞれ事件を追いかけ、再会は引っ張って引っ張って劇的に、っていう心憎い?演出もあるし1作目から見るに越したことは無い。
ただ、1作目に比べてミステリー要素が少し薄くなってアクション要素が濃くなっているので2作目から見ても楽しめる、はず。
2作目から登場する無痛症の巨人ニーダーマンも恐ろしいしね。金的にスタンガン食らわすという必殺技を受けても平然としている怪物だが、燃え盛る倉庫の裏から人が逃げていても気付かない間抜けさとか父に従順な姿等はお茶目だ。
無痛症だからスタンガンが利かない、プロボクサーのパンチを受けても倒れない、ハイキックを首にもろに何発食らっても倒れない、っていうのは「んな馬鹿な」って話だがお茶目だからいい。
登場人物がよく覚えられなくてちょっと苦労した。
呼ばれ方がfamily nameだったりfirst nameだったりするのでフルネームで覚えないといけない。
サランデルとサンドストレムとエクストレム、ビュルマンとビョルクとかどれが誰だっけ?ってムキーとしてくる。
終わり方が余韻無しなのは3部目に続くから。
2部と3部はテレビドラマ用に制作されていたが1作目が大ヒットしたのを受けて劇場用に編集しなおして公開したらしい。
テレビドラマ用だったためか登場人物の初登場シーンに字幕で名前紹介が出たりする。
「リスベット(天才ハッカー)」だ。今回ハッカーらしいことはほとんどしていなかった気がするが。
at ギンレイホール
![ミレニアム2 火と戯れる女 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/514pPyUpnJL._SL160_.jpg)
ミレニアム3部作の2作目。
130分もあるから覚悟していたけど、見終わったら「あれっもう終わってしまった」という感じ。
エンドロール中に振り返ってみるといろんなシーンが思い出されて確かに130分のボリュームがあったと納得する。
前作を見ていないと何がなんだか分らない点も結構あるだろうな。
私はサディストの豚ですとか。
ミカエルとリスベットがそれぞれ事件を追いかけ、再会は引っ張って引っ張って劇的に、っていう心憎い?演出もあるし1作目から見るに越したことは無い。
ただ、1作目に比べてミステリー要素が少し薄くなってアクション要素が濃くなっているので2作目から見ても楽しめる、はず。
2作目から登場する無痛症の巨人ニーダーマンも恐ろしいしね。金的にスタンガン食らわすという必殺技を受けても平然としている怪物だが、燃え盛る倉庫の裏から人が逃げていても気付かない間抜けさとか父に従順な姿等はお茶目だ。
無痛症だからスタンガンが利かない、プロボクサーのパンチを受けても倒れない、ハイキックを首にもろに何発食らっても倒れない、っていうのは「んな馬鹿な」って話だがお茶目だからいい。
登場人物がよく覚えられなくてちょっと苦労した。
呼ばれ方がfamily nameだったりfirst nameだったりするのでフルネームで覚えないといけない。
サランデルとサンドストレムとエクストレム、ビュルマンとビョルクとかどれが誰だっけ?ってムキーとしてくる。
終わり方が余韻無しなのは3部目に続くから。
2部と3部はテレビドラマ用に制作されていたが1作目が大ヒットしたのを受けて劇場用に編集しなおして公開したらしい。
テレビドラマ用だったためか登場人物の初登場シーンに字幕で名前紹介が出たりする。
「リスベット(天才ハッカー)」だ。今回ハッカーらしいことはほとんどしていなかった気がするが。
映画『アイスバーグ!』
2005年 監督:ドミニク・アベル、他
at ギンレイホール
予告編を見ていないので先日の『北京の自転車』みたいに思いがけなく面白い作品だったりして、と期待に胸を膨らまして見たわけですよ。
そういえばワンピースにアイスバーグさんっていたよなって考えながら。
冒頭氷の世界でアジア系の女性が正面から映され、彼女が言うには自分はイヌクティトゥット語を話せる最後の人間だと。
子供や夫にもこの言葉を覚えて欲しい。
私が夫とどのようにして出会ったかお話しましょう。
アイヌ系の女性なのか。
とにかくにこにこしていて、最後のセリフの後の無言の笑顔が素敵すぎて思わず泣きそうになる。
これはもしかして物凄く面白い映画なんじゃないか!
しかしそんな感動と期待をよそに場面はがらっと代わってヨーロッパ系のひょろっと背の高い初老のおばさんが現れる。
初老は言いすぎか。
体から油分が全て無くなって干からびたような感じだったので年いっているように見えたが、実際は40前後かもしれない。
それにしてもまた魅力のない女性が出てきたもんだ。
まあそれは置いといて気になるのはさっきからちょいちょい少しも面白くないサイレント風のギャグが織り交ぜられているのだが、これは一体なんなんだ?
このギャグはほんの気まぐれであってくれという願いもむなしく、最後までこんなギャグの連続で進んでいく。
もうこんなにつまらなくてきつい映画は久しぶりだ。
『死霊の盆踊り』がまだ面白く思えるくらい。
なにがきついってギャグが一つも面白くないどころかイラっとするから。
一度イラッとするとギャグはもとより食器のかちゃかちゃいう音とか目覚ましとかモザイクなしの陰部とか、もう全てにイラッとする。
この監督はアキ・カウリスマキやジャック・タチのような映画を目指していたのかもしれないが、比べるのもおこがましいほどの糞映画が生まれてしまった。
僕はどんな映画でも映画である以上それなりに最後まで鑑賞できる人だと思っていたけど、やっぱり合う合わないっていうのがあるとこの年になって初めて知った。
本当につまらなくて苦痛だったわ~。
監督は面倒だから他と略して書いたが、3人いる。
夫婦役の主演二人、ドミニク・アベルとフィオナ・ゴードン、そして村の雑貨屋みたいな店でいつも帳簿を付けているだけの主人役だったブルーノ・ロミの3人が共同監督している。
3人とも職業は道化師だそうだ。
小さい漁船"タイタニック号"の船長役のフィリップ・マルツも道化師。
ベルギー映画。
ギンレイで来週から上映される『ルンバ!』の予告編見たら出演しているのはどう見てもフィオナ・ゴードンだ。
監督も同じっぽい。
どうしよう。
at ギンレイホール
予告編を見ていないので先日の『北京の自転車』みたいに思いがけなく面白い作品だったりして、と期待に胸を膨らまして見たわけですよ。
そういえばワンピースにアイスバーグさんっていたよなって考えながら。
冒頭氷の世界でアジア系の女性が正面から映され、彼女が言うには自分はイヌクティトゥット語を話せる最後の人間だと。
子供や夫にもこの言葉を覚えて欲しい。
私が夫とどのようにして出会ったかお話しましょう。
アイヌ系の女性なのか。
とにかくにこにこしていて、最後のセリフの後の無言の笑顔が素敵すぎて思わず泣きそうになる。
これはもしかして物凄く面白い映画なんじゃないか!
しかしそんな感動と期待をよそに場面はがらっと代わってヨーロッパ系のひょろっと背の高い初老のおばさんが現れる。
初老は言いすぎか。
体から油分が全て無くなって干からびたような感じだったので年いっているように見えたが、実際は40前後かもしれない。
それにしてもまた魅力のない女性が出てきたもんだ。
まあそれは置いといて気になるのはさっきからちょいちょい少しも面白くないサイレント風のギャグが織り交ぜられているのだが、これは一体なんなんだ?
このギャグはほんの気まぐれであってくれという願いもむなしく、最後までこんなギャグの連続で進んでいく。
もうこんなにつまらなくてきつい映画は久しぶりだ。
『死霊の盆踊り』がまだ面白く思えるくらい。
なにがきついってギャグが一つも面白くないどころかイラっとするから。
一度イラッとするとギャグはもとより食器のかちゃかちゃいう音とか目覚ましとかモザイクなしの陰部とか、もう全てにイラッとする。
この監督はアキ・カウリスマキやジャック・タチのような映画を目指していたのかもしれないが、比べるのもおこがましいほどの糞映画が生まれてしまった。
僕はどんな映画でも映画である以上それなりに最後まで鑑賞できる人だと思っていたけど、やっぱり合う合わないっていうのがあるとこの年になって初めて知った。
本当につまらなくて苦痛だったわ~。
監督は面倒だから他と略して書いたが、3人いる。
夫婦役の主演二人、ドミニク・アベルとフィオナ・ゴードン、そして村の雑貨屋みたいな店でいつも帳簿を付けているだけの主人役だったブルーノ・ロミの3人が共同監督している。
3人とも職業は道化師だそうだ。
小さい漁船"タイタニック号"の船長役のフィリップ・マルツも道化師。
ベルギー映画。
ギンレイで来週から上映される『ルンバ!』の予告編見たら出演しているのはどう見てもフィオナ・ゴードンだ。
監督も同じっぽい。
どうしよう。
2011年1月4日火曜日
映画『ヤギと男と男と壁と』
2009年 監督:グラント・ヘスロヴ
at ギンレイホール
![ヤギと男と男と壁と [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517446jNXlL._SL160_.jpg)
ヤギと男と男と壁と
CSの番組で千原ジュニアが付けたという邦題。
酒と泪と男と女みたいだ。
原題は
THE MEN WHO STARE AT GOATS
直訳すると
ヤギを見詰める男性
かなぁ。
原作はジョン・ロンスンのノンフィクション『実録・アメリカ超能力部隊』で、本のタイトルにもあるようにアメリカで実在したとかしないとかいう超能力部隊"新地球軍"を扱った物語。
超能力、といってもCGばりばりのハイパーエスパー軍団が大活躍するようなSFじゃなくて、ノンフィクションなのでもう少し現実的。
といってもなんたって"ジェダイ計画"により生まれた"新地球軍"は隅から隅までヒッピーで成り立っているのでシニカルな笑いを交えつつアメリカ人と戦争が描かれていく。
2003年、新聞記者のボブ(ユアン・マクレガー)は妻を編集長に取られた腹いせにイラク戦争の取材を敢行する。
そして入国前に立ち寄ったクウェートでリン(ジョージ・クルーニー)という男と出会い、一緒にイラクに入国する。
リンはかつて新地球軍でNo.2の実力を持った優秀なエスパー戦士だった。
イラクでの二人の動向とリンにより語られる超能力部隊の清濁併せ持つ歴史が交互に描かれる。
ラストの解放のシーンで爽快感よりもの寂しさを感じるのは何故だろう。
時代に取り残されたヒッピーの成れの果てを見ているからか。
新地球軍のリーダーだったビル(ジェフ・ブリッジス)もアル中のおっさんだ。
肝心の超能力もリンの過去語りで片鱗が少し覗く程度なので、実は現在のリンは超能力を失った(もしくは最初から超能力を持っていなかった)と考えると、過去にしがみつき見得で生きているような寂しさもある。
全体通して言えるのは、ベトナム人もイラク人も皆真面目の中、アメリカ人だけがどこか不真面目(本人達は真面目だが)でアイロニカルに浮いている。
ラストの解放もイラク人から見たら虐待するのも解放するのも同じアメリカ人だ。
アメリカの自己批判が哀愁漂うおっさん達の強烈なキャラクターで後ろ向きにも前向きにも見える不思議なストーリー。
→おっさん達、とはジョージ・クルーニー+ジェフ・ブリッジス+ケヴィン・スペイシー。
at ギンレイホール
![ヤギと男と男と壁と [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517446jNXlL._SL160_.jpg)
ヤギと男と男と壁と
CSの番組で千原ジュニアが付けたという邦題。
酒と泪と男と女みたいだ。
原題は
THE MEN WHO STARE AT GOATS
直訳すると
ヤギを見詰める男性
かなぁ。
原作はジョン・ロンスンのノンフィクション『実録・アメリカ超能力部隊』で、本のタイトルにもあるようにアメリカで実在したとかしないとかいう超能力部隊"新地球軍"を扱った物語。
超能力、といってもCGばりばりのハイパーエスパー軍団が大活躍するようなSFじゃなくて、ノンフィクションなのでもう少し現実的。
といってもなんたって"ジェダイ計画"により生まれた"新地球軍"は隅から隅までヒッピーで成り立っているのでシニカルな笑いを交えつつアメリカ人と戦争が描かれていく。
2003年、新聞記者のボブ(ユアン・マクレガー)は妻を編集長に取られた腹いせにイラク戦争の取材を敢行する。
そして入国前に立ち寄ったクウェートでリン(ジョージ・クルーニー)という男と出会い、一緒にイラクに入国する。
リンはかつて新地球軍でNo.2の実力を持った優秀なエスパー戦士だった。
イラクでの二人の動向とリンにより語られる超能力部隊の清濁併せ持つ歴史が交互に描かれる。
ラストの解放のシーンで爽快感よりもの寂しさを感じるのは何故だろう。
時代に取り残されたヒッピーの成れの果てを見ているからか。
新地球軍のリーダーだったビル(ジェフ・ブリッジス)もアル中のおっさんだ。
肝心の超能力もリンの過去語りで片鱗が少し覗く程度なので、実は現在のリンは超能力を失った(もしくは最初から超能力を持っていなかった)と考えると、過去にしがみつき見得で生きているような寂しさもある。
全体通して言えるのは、ベトナム人もイラク人も皆真面目の中、アメリカ人だけがどこか不真面目(本人達は真面目だが)でアイロニカルに浮いている。
ラストの解放もイラク人から見たら虐待するのも解放するのも同じアメリカ人だ。
アメリカの自己批判が哀愁漂うおっさん達の強烈なキャラクターで後ろ向きにも前向きにも見える不思議なストーリー。
→おっさん達、とはジョージ・クルーニー+ジェフ・ブリッジス+ケヴィン・スペイシー。
映画『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』
2009年 監督:トッド・フィリップス
at ギンレイホール
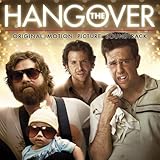
長いタイトルだ。
結婚式当日、新郎の友人から花嫁に電話がかかる。
だだっ広い砂漠の一本道からの電話で告げられる「花婿は欠席するかも・・・」という知らせ。
花婿が消えてしまったらしい。
なにやらミステリー。
という真面目さはオープニングだけで、ミステリーはミステリーだけどノリはハイテンションなドタバタコメディ。
バチェラー・パーティでラスベガスに繰り出した男4人が最高級ホテルのスイートで目覚めると、部屋はぐちゃぐちゃ、鶏はいるは虎がいるは赤ん坊はいるは歯がなくなっているは花婿はいないはで昨夜のはちゃめちゃぶりが伺えるのだけど、当の本人達は揃って記憶を無くしている。
分らないことだらけだけど、とにかく花婿のダグを探さないと。
手がかりを求めて昨夜の足跡を辿る衝撃の旅が始まる。
途中ちょっと飽きてきたけど、面白いのは登場人物が最悪(最高)の一夜とそれを追う旅を通して成長しているところ。
いい年のおっさん達に成長っていうのもなんだけど。
記憶を失くした夜が非日常なら非日常でこそ本当の顔がさらけ出される。
目覚めた日は非日常と日常の狭間にあり、その中間点をいったりきたり彷徨う過程で表と裏の顔が馴染んでいく。
だからその過程を経なかった行方不明の花婿ダグは代わりに黒くなった。。。
爆笑するほど笑うことはなかったけど、あのエンドロールには思わず笑ってしまったな。
ステュ(エド・ヘルムズ)
真面目で一番理知的そうな歯科医。
ただ、あのたるみきった汚い肉体を見た瞬間、速攻イメージが崩壊する。
最悪の夜に一番はっちゃけてとんでもない行為をし続けていたのはステュだった。
フィル(ブラッドリー・クーパー)
小学校の教師ながら一番下品な男。
そして一番の色男。
独身生活を謳歌していそうでいながら妻子持ちだったりする。
軽くて適当な男と思いきや、実は至極冷静で優しい男だった。
アラン(ザック・ガリフィナーキス)
花嫁の弟で、ステュとフィルと一応面識はあるという程度。
ただ、変なパンツを履いているから変な奴なんだろう。
何をしでかしたか知らないが小学校とコンビニに接近禁止命令が出ているらしい。
花婿の親友達に突然混ざっても臆すどころか勝手に乾杯の音頭を取って一匹狼の"軍団"に三匹が加わったなどとのたまう。
最終的にはフィルに憧れる可愛い奴。
ザック・ガリフィナーキスは若いのかと思ったら調べてみると実年齢は飛びぬけて高かった。
ストリッパー役でヘザー・グレアムが出ている。
いつの間にかもう40だよ、この人。
それなのになんでもないことのように普通におっぱい出している。
がん見するアラン。
あとマイク・タイソンが本人役で出演している。
予告編でドラムの音に合わせてエアドラムをした流れでそのまま殺人パンチを放つ流れが爽快だったのに、あれは予告編のみの編集だった。
このドラムが印象的な曲はフィル・コリンズの『In the Air Tonight』、らしい。
上映前の劇場のBGMで妙に懐かしい曲ばかりかかっていて、フィル・コリンズ時代のジェネシスの『インヴィジブル・タッチ』も流れていたが、『In the Air Tonight』つながりでかけていたのかな。
at ギンレイホール
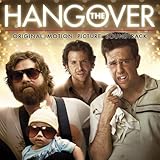
長いタイトルだ。
結婚式当日、新郎の友人から花嫁に電話がかかる。
だだっ広い砂漠の一本道からの電話で告げられる「花婿は欠席するかも・・・」という知らせ。
花婿が消えてしまったらしい。
なにやらミステリー。
という真面目さはオープニングだけで、ミステリーはミステリーだけどノリはハイテンションなドタバタコメディ。
バチェラー・パーティでラスベガスに繰り出した男4人が最高級ホテルのスイートで目覚めると、部屋はぐちゃぐちゃ、鶏はいるは虎がいるは赤ん坊はいるは歯がなくなっているは花婿はいないはで昨夜のはちゃめちゃぶりが伺えるのだけど、当の本人達は揃って記憶を無くしている。
分らないことだらけだけど、とにかく花婿のダグを探さないと。
手がかりを求めて昨夜の足跡を辿る衝撃の旅が始まる。
途中ちょっと飽きてきたけど、面白いのは登場人物が最悪(最高)の一夜とそれを追う旅を通して成長しているところ。
いい年のおっさん達に成長っていうのもなんだけど。
記憶を失くした夜が非日常なら非日常でこそ本当の顔がさらけ出される。
目覚めた日は非日常と日常の狭間にあり、その中間点をいったりきたり彷徨う過程で表と裏の顔が馴染んでいく。
だからその過程を経なかった行方不明の花婿ダグは代わりに黒くなった。。。
爆笑するほど笑うことはなかったけど、あのエンドロールには思わず笑ってしまったな。
ステュ(エド・ヘルムズ)
真面目で一番理知的そうな歯科医。
ただ、あのたるみきった汚い肉体を見た瞬間、速攻イメージが崩壊する。
最悪の夜に一番はっちゃけてとんでもない行為をし続けていたのはステュだった。
フィル(ブラッドリー・クーパー)
小学校の教師ながら一番下品な男。
そして一番の色男。
独身生活を謳歌していそうでいながら妻子持ちだったりする。
軽くて適当な男と思いきや、実は至極冷静で優しい男だった。
アラン(ザック・ガリフィナーキス)
花嫁の弟で、ステュとフィルと一応面識はあるという程度。
ただ、変なパンツを履いているから変な奴なんだろう。
何をしでかしたか知らないが小学校とコンビニに接近禁止命令が出ているらしい。
花婿の親友達に突然混ざっても臆すどころか勝手に乾杯の音頭を取って一匹狼の"軍団"に三匹が加わったなどとのたまう。
最終的にはフィルに憧れる可愛い奴。
ザック・ガリフィナーキスは若いのかと思ったら調べてみると実年齢は飛びぬけて高かった。
ストリッパー役でヘザー・グレアムが出ている。
いつの間にかもう40だよ、この人。
それなのになんでもないことのように普通におっぱい出している。
がん見するアラン。
あとマイク・タイソンが本人役で出演している。
予告編でドラムの音に合わせてエアドラムをした流れでそのまま殺人パンチを放つ流れが爽快だったのに、あれは予告編のみの編集だった。
このドラムが印象的な曲はフィル・コリンズの『In the Air Tonight』、らしい。
上映前の劇場のBGMで妙に懐かしい曲ばかりかかっていて、フィル・コリンズ時代のジェネシスの『インヴィジブル・タッチ』も流れていたが、『In the Air Tonight』つながりでかけていたのかな。
2011年1月3日月曜日
映画『スウィングガールズ』
2004年 監督:矢口史靖
DVD
![スウィングガールズ スタンダード・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517VNAFVZPL.jpg)
数年前に会社の同僚に借りて、見よう見ようと思っていたDVDをやっと見る。
ネットで調べてみるとなぜかあまり評判がよくないんだな。
面白いのに。
楽譜も読めない楽器の初心者達が有能な講師がいるわけでもなく、名演奏を聞きこんでいるわけでもなく、そんなに練習している風でもないのにいつの間にか高校生とは思えないレベルのビッグバンドに成長している不思議。
指導に当たる教師はレコードマニアだが楽器未経験でかつ致命的に音楽の才能が無い。
上手くなるには唯一の経験者の拓雄君が頼りだが、彼は元パーカスで管楽器の経験が無い上に、ど下手な演奏に何も不満も湧かないほどの音痴だった。
というように上手くなる要素が微塵も無いところに突っ込みつつも、そんなことどうでもいいくらいの要素が二つある。
一つ目はなんといっても上野樹里の小憎たらしいはっちゃけっぷりで、『チルソクの夏』やジョゼの真面目さと、変人寄りだったのだめとの中間の丁度いい自由さ。
高校生の成長譚、といっても無気力で自分勝手に生きていた少女が打ち込めるものを見つけて大事な仲間も得る、ということ以外何がどう成長したのかは不明なものの、ヒロインの表情豊かな若い魅力は『ロボコン』の長澤まさみに匹敵する。
矢口映画のヒロインは西田尚美しかいないと思っていたけど上野樹里もぴったりだ。
二つ目は矢口史靖独特のリズム感で、それがストーリーの突っ込みどころにもなるのだけど、とにかく場面展開の素早いリズム感が心地いい。
短いカットの中にも強烈なキャラクターの登場人物達がシーンの隅々で何気なくかつ奔放に動いていて結構濃密だったりもする。
お得意の人形を使ったギャグもあり。
そして基本的には馬鹿ノリで紡がれる矢口監督の演出にはめずらしく、それまでのノリが一変して時間が止まったかのように静謐になる短いシーンがある。
このシーンの上野樹里の美しいこと。
滅茶苦茶かわいいというわけでもない上野樹里がその生涯を通して一番美しい顔した瞬間だったんじゃないかと思うくらい神秘的なシーン。
この唯一の異質なシーンが作品全体に楔のように作用して、軽妙なノリの奥に潜む隙間をじわじわ埋めていくから作品が重層的になり面白くなっている。
このシーンがなかったら『ウォーターボーイズ』みたいにパッと見てパッと楽しんでパッと忘れてしまったかもしれない。
最後の演奏シーンは絶対吹き替えだと思っていた。
部活で3年間みっちり練習してもこれほど吹けるようになる人は稀なのに、撮影で初めて楽器を手にしたと思われる出演者達がこんなに吹けるようになるわけがない。
ただ、指使いとかアンブシュアとか本当っぽく様になっているなぁと思っていたら、様になっているどころか本当に彼女達が演奏していたらしい。
クランクイン前から練習していたというが、それにしても驚きだ。
このDVDは特典で監督や出演者の解説が副音声で聞けるようになっている。
しかも2パターン。
105分丸まる付いているから後2回見なくては。
見終わってからそういえばこの映画は松田まどかが出ていたはずと思って見直したら、本当に全く目立たない役でバリトンサックス吹いていた。
ファミリーマートが印象的な名作『NAGISA なぎさ』でデビュー作ながら主役張っていたのになぁ。
DVD
![スウィングガールズ スタンダード・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517VNAFVZPL.jpg)
数年前に会社の同僚に借りて、見よう見ようと思っていたDVDをやっと見る。
ネットで調べてみるとなぜかあまり評判がよくないんだな。
面白いのに。
楽譜も読めない楽器の初心者達が有能な講師がいるわけでもなく、名演奏を聞きこんでいるわけでもなく、そんなに練習している風でもないのにいつの間にか高校生とは思えないレベルのビッグバンドに成長している不思議。
指導に当たる教師はレコードマニアだが楽器未経験でかつ致命的に音楽の才能が無い。
上手くなるには唯一の経験者の拓雄君が頼りだが、彼は元パーカスで管楽器の経験が無い上に、ど下手な演奏に何も不満も湧かないほどの音痴だった。
というように上手くなる要素が微塵も無いところに突っ込みつつも、そんなことどうでもいいくらいの要素が二つある。
一つ目はなんといっても上野樹里の小憎たらしいはっちゃけっぷりで、『チルソクの夏』やジョゼの真面目さと、変人寄りだったのだめとの中間の丁度いい自由さ。
高校生の成長譚、といっても無気力で自分勝手に生きていた少女が打ち込めるものを見つけて大事な仲間も得る、ということ以外何がどう成長したのかは不明なものの、ヒロインの表情豊かな若い魅力は『ロボコン』の長澤まさみに匹敵する。
矢口映画のヒロインは西田尚美しかいないと思っていたけど上野樹里もぴったりだ。
二つ目は矢口史靖独特のリズム感で、それがストーリーの突っ込みどころにもなるのだけど、とにかく場面展開の素早いリズム感が心地いい。
短いカットの中にも強烈なキャラクターの登場人物達がシーンの隅々で何気なくかつ奔放に動いていて結構濃密だったりもする。
お得意の人形を使ったギャグもあり。
そして基本的には馬鹿ノリで紡がれる矢口監督の演出にはめずらしく、それまでのノリが一変して時間が止まったかのように静謐になる短いシーンがある。
このシーンの上野樹里の美しいこと。
滅茶苦茶かわいいというわけでもない上野樹里がその生涯を通して一番美しい顔した瞬間だったんじゃないかと思うくらい神秘的なシーン。
この唯一の異質なシーンが作品全体に楔のように作用して、軽妙なノリの奥に潜む隙間をじわじわ埋めていくから作品が重層的になり面白くなっている。
このシーンがなかったら『ウォーターボーイズ』みたいにパッと見てパッと楽しんでパッと忘れてしまったかもしれない。
最後の演奏シーンは絶対吹き替えだと思っていた。
部活で3年間みっちり練習してもこれほど吹けるようになる人は稀なのに、撮影で初めて楽器を手にしたと思われる出演者達がこんなに吹けるようになるわけがない。
ただ、指使いとかアンブシュアとか本当っぽく様になっているなぁと思っていたら、様になっているどころか本当に彼女達が演奏していたらしい。
クランクイン前から練習していたというが、それにしても驚きだ。
このDVDは特典で監督や出演者の解説が副音声で聞けるようになっている。
しかも2パターン。
105分丸まる付いているから後2回見なくては。
見終わってからそういえばこの映画は松田まどかが出ていたはずと思って見直したら、本当に全く目立たない役でバリトンサックス吹いていた。
ファミリーマートが印象的な名作『NAGISA なぎさ』でデビュー作ながら主役張っていたのになぁ。
2011年1月2日日曜日
映画『死霊の盆踊り』
1965年 監督:A・C・スティーヴン
DVD
![死霊の盆踊り デラックス版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31K1FK0VXCL.jpg)
『マタンゴ』に終わり『死霊の盆踊り』で始まるあけましておめでとうございます。
数年前に友人に借りて、見よう見ようと思っていた(かは定かではないが)DVDをやっと見る。
『死霊の盆踊り』って間違いなく日本向けの邦題で、そんな邦題付ける時点でB級映画臭がぷんぷんする。
冒頭棺桶から目覚めたおっさんがうつむき加減の寝ぼけ眼で言うには「これから話す物語は気を失うほどに恐ろしい」らしい。
クレジットタイトルを見ていると、
Gold Girl Dance
Hawaian Dance
Skelton Dance
Indian Dance
Slave Dance
などとキャスト紹介されている。
なんのことやら分らずにいると、MummyとかWolf Manという文字も見えるから一応ホラー映画っぽくて安心する。
いや、そもそもクレジットタイトルのバックの静止画が全身金粉塗った裸の女という事実から目を逸らしてはいけない。
続けて
Screenplay by EDWARD D,WOOD,JR.
という文字を見たらもう観念するしかない。
ストーリーは、ストリッパーを劇場じゃなくて墓場で躍らせたら面白いんじゃない?というもの。
ああ、コンセプトじゃなくてストーリーの説明か。
ショーツを履いただけの女達が延々と踊ります。
一応夜の帝王と闇の女王がいて、夜の帝王という役のエロおやじを喜ばすために、闇の女王が若い女性(死霊)に裸踊りをさせるという設定がある。
そしてその”盆踊り大会”に墓場で事故ったバカップルが巻き込まれる(というか特等席で鑑賞させられ男の方なんてニヤついている)という設定もある。
最低限の設定はあってもストーリーは無い。
91分のうちの大半は裸踊りだ。
しかも踊りがつまらない!
花嫁ダンサーなんか乳ぶるぶる震わせてるだけだし。
なんとか寝ずに最後まで見たが、もう一度見ろと言われたら全力で回避する。(ながら見ならできそうだが)
DVDには特典で監督のインタビューが付いている。
エドウッドはいい脚本家だが監督の才能は全くないね、と。
クレジットタイトル後の夕方だか夜だか昼だか入り乱れてよく分らないシーンは現像技師のミスだと言い訳していた。
いや、もう昼と夜がごっちゃになっているのなんて作品全体のしょうもなさを見た後では何の弁解にもならない。
ダンスシーンの音楽は後からオリジナルの曲に差し替えたとのこと。
おかげでただでさえつまらないダンスが音楽に合わなくなってさらにわけ分らなくなった。
確信犯だ。。。
夜の帝王役のクリスウェルは若い頃はさぞかし美男子だっただろう。
年いっている割には子供のような表情しているのが少し普通じゃない気もする。
それもそのはず、彼は1950年代にTVで一世を風靡していた自称霊能者かつ予言者、という怪しげな経歴。
エドウッドの作品にも出演しているらしい。
セリフを覚えない男らしく、カンニングペーパーを見て撮影したシーンもあるそうだ。
冒頭なんか正しくそうだろう。
寝起きでたるそう感じは下にあるカンニングペーパーを見ていたからか!
そういえばティム・バートンの『エド・ウッド』で棺桶で寝起きする男が出ていた気がするが、あれがクリスウェルだったのかな。
ヒロインのカップルの女の方が最後に闇の女王によりブラウスをはだけさせられ、かつブラジャーの真ん中を小刀でぷっつり切られるのだけど、ブラジャーがぱつんと大きく観音開きするかと思いきや胸にぴったりくっついたままで乳首が出ない。
おっぱいの見すぎで食傷気味のところで最後の最後で微妙な消化不良。
監督インタビューによると、闇の女王役のファウン・シルヴァーは唯一脱がない女優だったそうだが、ヒロインも脱がなかったから二人じゃないの?と思ったら、ヒロインとGold Girl Danceは同一人物だったらしい。
Gold Girl Danceが踊っているのを同一人物のヒロインが見下ろしていたんだね。
なかなかやるな。
ORGY OF THE DEAD
が原題。
死者の乱交パーティーとでも訳すのか。
死霊の盆踊りと大して変わらなかった。
邦題は江戸木純が付けている。
DVD
![死霊の盆踊り デラックス版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31K1FK0VXCL.jpg)
『マタンゴ』に終わり『死霊の盆踊り』で始まるあけましておめでとうございます。
数年前に友人に借りて、見よう見ようと思っていた(かは定かではないが)DVDをやっと見る。
『死霊の盆踊り』って間違いなく日本向けの邦題で、そんな邦題付ける時点でB級映画臭がぷんぷんする。
冒頭棺桶から目覚めたおっさんがうつむき加減の寝ぼけ眼で言うには「これから話す物語は気を失うほどに恐ろしい」らしい。
クレジットタイトルを見ていると、
Gold Girl Dance
Hawaian Dance
Skelton Dance
Indian Dance
Slave Dance
などとキャスト紹介されている。
なんのことやら分らずにいると、MummyとかWolf Manという文字も見えるから一応ホラー映画っぽくて安心する。
いや、そもそもクレジットタイトルのバックの静止画が全身金粉塗った裸の女という事実から目を逸らしてはいけない。
続けて
Screenplay by EDWARD D,WOOD,JR.
という文字を見たらもう観念するしかない。
ストーリーは、ストリッパーを劇場じゃなくて墓場で躍らせたら面白いんじゃない?というもの。
ああ、コンセプトじゃなくてストーリーの説明か。
ショーツを履いただけの女達が延々と踊ります。
一応夜の帝王と闇の女王がいて、夜の帝王という役のエロおやじを喜ばすために、闇の女王が若い女性(死霊)に裸踊りをさせるという設定がある。
そしてその”盆踊り大会”に墓場で事故ったバカップルが巻き込まれる(というか特等席で鑑賞させられ男の方なんてニヤついている)という設定もある。
最低限の設定はあってもストーリーは無い。
91分のうちの大半は裸踊りだ。
しかも踊りがつまらない!
花嫁ダンサーなんか乳ぶるぶる震わせてるだけだし。
なんとか寝ずに最後まで見たが、もう一度見ろと言われたら全力で回避する。(ながら見ならできそうだが)
DVDには特典で監督のインタビューが付いている。
エドウッドはいい脚本家だが監督の才能は全くないね、と。
クレジットタイトル後の夕方だか夜だか昼だか入り乱れてよく分らないシーンは現像技師のミスだと言い訳していた。
いや、もう昼と夜がごっちゃになっているのなんて作品全体のしょうもなさを見た後では何の弁解にもならない。
ダンスシーンの音楽は後からオリジナルの曲に差し替えたとのこと。
おかげでただでさえつまらないダンスが音楽に合わなくなってさらにわけ分らなくなった。
確信犯だ。。。
夜の帝王役のクリスウェルは若い頃はさぞかし美男子だっただろう。
年いっている割には子供のような表情しているのが少し普通じゃない気もする。
それもそのはず、彼は1950年代にTVで一世を風靡していた自称霊能者かつ予言者、という怪しげな経歴。
エドウッドの作品にも出演しているらしい。
セリフを覚えない男らしく、カンニングペーパーを見て撮影したシーンもあるそうだ。
冒頭なんか正しくそうだろう。
寝起きでたるそう感じは下にあるカンニングペーパーを見ていたからか!
そういえばティム・バートンの『エド・ウッド』で棺桶で寝起きする男が出ていた気がするが、あれがクリスウェルだったのかな。
ヒロインのカップルの女の方が最後に闇の女王によりブラウスをはだけさせられ、かつブラジャーの真ん中を小刀でぷっつり切られるのだけど、ブラジャーがぱつんと大きく観音開きするかと思いきや胸にぴったりくっついたままで乳首が出ない。
おっぱいの見すぎで食傷気味のところで最後の最後で微妙な消化不良。
監督インタビューによると、闇の女王役のファウン・シルヴァーは唯一脱がない女優だったそうだが、ヒロインも脱がなかったから二人じゃないの?と思ったら、ヒロインとGold Girl Danceは同一人物だったらしい。
Gold Girl Danceが踊っているのを同一人物のヒロインが見下ろしていたんだね。
なかなかやるな。
ORGY OF THE DEAD
が原題。
死者の乱交パーティーとでも訳すのか。
死霊の盆踊りと大して変わらなかった。
邦題は江戸木純が付けている。
登録:
コメント (Atom)

