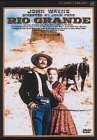寿美さんの歌を聴くのが生きがいです。
仕事を早退して渋谷公会堂へ。
渋谷駅から人ごみの流れに沿って歩く。
渋谷公会堂に近づくにつれ、人の波は若者より年配の人が増えてくる。
少しだけひるみながらも会場に入る。
チケットに記載された席は7列目。探していると前の方の席はほとんど人で埋まっているのを見て、探すのをやめてロビーに戻る。
禁煙マークが見えるがマークの側に「喫煙は所定の場所で」と書いてある。喫煙所を探して1階2階をうろうろするが見つからず、1階の非常口らしきドアの前にいた係員に喫煙所を聞く。
全館禁煙とのこと。でも「どうしても我慢できないようであればこちらへどうぞ」と言われドアの外に案内してくれる。
どうしても吸いたいといえば吸いたいのだけど・・・
雨上がりの空を見上げながら1本愛しく吸う。
会場に戻り自分の座席を探す。ステージに向かって右端から3つ目だった。
開演まで待つ。
左隣には高校生くらいの若い女の子が座っている。右隣には長靴がキュートな小柄なおばちゃん。
傘を杖のようにして暫くぼーっとしていると、おばちゃんが「傘ここ置いていいよ」と言う。前の座席に沿って傘を置かしてくれた。
「どうもすいません。ありがとうございます」
「あのぅ、山内恵介さんですか?」
「えっ?」おばちゃんと目が合う。
「いえ、全然違いますよ。ははは。」
Yシャツネクタイのどっからどうみてもくたびれたサラリーマンの兄ちゃんつかまえて山内恵介とは面食らう。似ても似つかない。周りの人たちに比べて少し若いってだけで間違えた?
彼女の親切は俺を山内恵介だと思ったからなのかなぁ?
それにしても第二の美川憲一と密かに思っている山内恵介と間違われるとは。
いよいよ始まる。
1曲目はデビュー曲『女・・・ひとり旅』
おお!
となりの女の子がマリアを拝んでいるかのように手を合わせた状態で口パクで歌ってる!!
何者だ。田川寿美を目標に演歌歌手を目指している女の子なのか!
そうこう気をとられているうちに曲が終わってしまう。
それだけじゃなくてスピーカーから流れる音になんか違和感感じる。
オケは必要最小限で、ヴァイオリン、エレキ、ソプラノサックスやアルトサックスやフルート(←1人でやってた)、キーボード、ドラム、あとなんかあったかな。ベースもいたか。とりあえず全部一人づつ。
オケの音が聞こえすぎるくらいに聞こえたからうざかったのか、演奏が下手だったのか、演奏のバランスが悪かったか、寿美さんの声量にマイクが耐え切れず時折音が割れているように聞こえたからか。原因の特定が結局最後までできなかったんだけど。
席がはじっこの方でスピーカーのすぐ近くだった事も聞こえてくる音の違和感になったのかもしれない。
そもそもコンサートってクラシック等の生音でしか体験した事なくて(こないだのキュピキュピを除けば)、スピーカーで増幅されたコンサートって始めてだからただ戸惑ったのかもしれない。
次に初期の曲を3曲『思い出岬』『雪舞い列車』(←初めて聴いたがかなりの名曲)『みれん海峡』でデビュー当時からの足音を聞き、そして「華観月」「しゃくなげの雨」で会場を華で満たす。
→衣装チェンジ
ユーモアに溢れた司会のおじさんが場を繋ぐ。ラジオ「華のうた」の会話が流れたりもする。
何分も待った後、イントロが始まった。
寿美さんが登場してくる。その姿を見て息を呑む。
ワインレッドのドレスを纏い、華麗にステップを踏んで舞台中央に進む姿のなんという華やかさ。
華麗に、華麗な、とかちょっとでも動作や行動がかっこよかったりすると簡単に使う言葉だけど、本当に"華麗"な人って見たことあるだろうか。人に呼吸を忘れて見とれさせるほどの。
衝撃はまだ続く。
登場してきて歌った曲が『本牧メルヘン』でこれがまた哀愁の含んだ声で熱情的に歌っているのさ。感動とか通り越して震えてくる。
(「本牧メルヘン」は作詞 阿久悠/作曲 井上忠夫で鹿内孝が歌っていた。GS全盛期にヒットしたソロ曲。)
続けて因幡晃の『わかって下さい』。「涙で、文字が 滲んでいたーならー わかあてー くださいー」の切ない歌声とフレーズが頭から離れない。
一転古い叙情歌を。北原白秋の『砂山』と『城ヶ島の雨』。
歌声がじっくり聴けていい。これらの曲を聴かせられる歌手ってそういないだろう。歌声や情感がむき出しでさらされるから実力がないと聴いてられないだろうし。
『忘れな草をあなたに』そしてシャンソン『サントワマミ』。
『サントワマミ』はどこまでも伸びやかに広がっていく歌唱と可愛らしい声の歌唱の対比が正に「夢のような~」素晴らしさ。
この時だったかな、歌いながら舞台袖の方に歩いていき、歌い終わった瞬間にぴょんと飛び跳ねるようにして袖に消えていった。夢のように。
→衣装チェンジ
ピアノと寿美さん自らのギター弾き語り。
ドリカムの『やさしいキスをして』。なんでこんなにかっこいいのか。シンプルな演奏で歌が映える。
そして『ひばりの佐渡情話』。
これは凄い。何度か寿美さんが歌っているのを聴いた事があるのだけど今までで最高の歌唱だったと思う。
今までは上手に歌っていた感があったけど、今回はかなりいい意味でフォームを崩して歌っている。
基礎のしっかりした人が殻をやぶって自由に羽ばたきだしたらもう誰もかなわない。
今後も年を重ねるごとに常に衝撃と感動を与え続けてくれるであろう田川寿美に対する期待と、今耳から入って全身をしびれさせている奔放で力強い迫力の歌唱で胸がいっぱいになる。
次にギターを置いてピアノ伴奏のみで『初めから今まで』。冬のソナタの主題歌。
冬のソナタも見てないしこの曲はそれほど耳にしたことないのだけど、間違いなくオリジナル歌手よりかは上手いだろうな。持ち歌みたいに歌いこなしている。ハングル語で。
田川寿美の華やかさを見ていると、他の若手女性歌手が皆田舎娘に見えてくるのだけど、かといって寿美さんは都会の人って感じもしない。京都も少し違う。
無国籍なんだよね。和歌山出身の日本人で演歌歌手であることは確かなんだけど、日本人でもどの国の人でもないような。むしろ確かに今を生きている一人の人間でありながら、人間の域を超えた存在といった感じか。
→衣装チェンジ
紫の着物で登場。
『こぼれ月』そして『悲しい歌はきらいですか』。
私が一番気に入ってる曲『悲しい歌はきらいですか』は芯からざわざわ震えが来るほどの衝撃。
今までと歌い方が違う。語尾はくっきりと切って語りかけるように、かつサビは伸びやかに、流麗に。
歌で観客を空間ごと包み込んでしまうのは美空ひばりと田川寿美くらいなもんだ。
『浅野川恋歌』『雑草の泪』『哀愁港』『北海岸』『海鳴り』着物姿でしっとりと。
→衣装チェンジ
衣装チェンジの間、司会の話から次の曲は『女人高野』だと知る。
舞台が光で照らされると寿美さんの姿が浮かび上がる。『女人高野』の衣装は少々飽きていたけど今回は衣装が違うではないか。
うろ覚えのため印象で書くと、天草四郎時貞の女性版みたいな。
エレキギターをかき鳴らした寿美さんから迸る熱情。迫力の歌唱。しびれるほどかっこいい。
そしてこのハードロック調の変な曲で唯一演奏と歌のバランスよい合致を感じる。
おお、もうラストだ。最後は一番新しい曲『花になれ』。
「すきな きせーつに ああ~ぁはなーになれ~」
夢の時間をひきずりながら渋谷の街を駅に向かって歩く。
田川寿美の生声聞いて、この人のファルセット(裏声)について認識した事。
TVやCDで聴いていた限り、寿美さんの裏声は魅力的なんだけど、裏声になるとパワーダウンしている気がしないでもない。
しかしなんだ、パワーダウンどころか地声よりパワフルだったりするじゃない。そして裏声まで見事にコントロールしているから力強かったり柔らかだったりと非常に表現も豊か。
裏声使いの名手寿美さんは曲中結構たくさん裏声を使うのだけど、裏声になると声の響きと麗しさが倍増しに広がる。
他の歌手のファルセットと違うのは声の響きが尋常じゃない事で、TV等で聴いているとこの響きは完全に伝わってこない。
地声の響きと麗しさにターボがかかった生ファルセットはとろける陶酔感を与えてくれる。
ああこりゃもう中毒だよ。